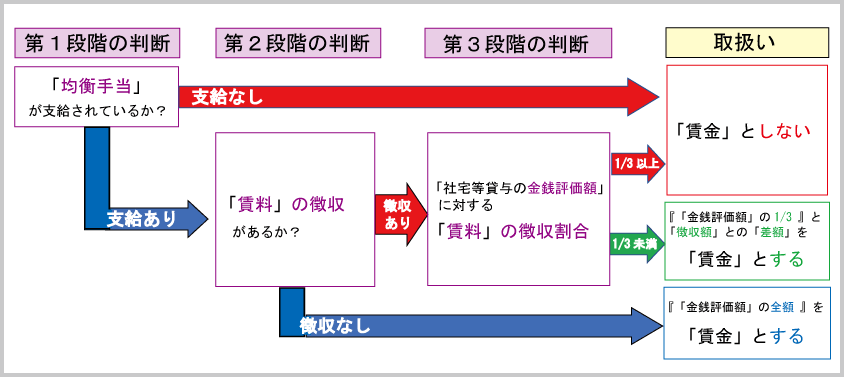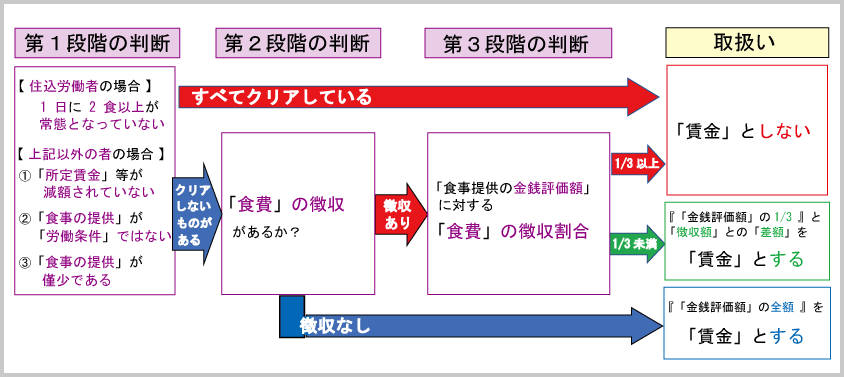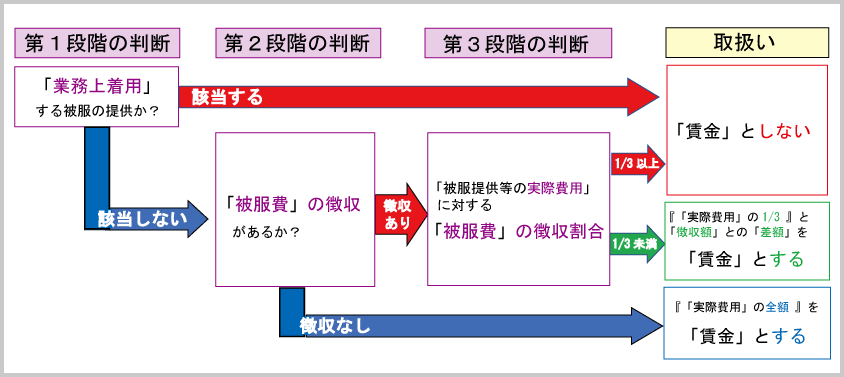ここでは『 給与計算で控除する「雇用保険料の具体的な計算方法」』につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページは『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』というページを補完するものとなります。
Ⅰ:「雇用保険料の控除計算」を行う前に必要となる確認事項
給与計算において「雇用保険料控除額」を算定する場合には、事前に、
|
1、雇用保険料の控除計算が必要となる「従業員の範囲」
2、雇用保険料控除額の算定基礎となる「賃金の範囲」
3、雇用保険料控除額の算定基礎となる「(従業員が負担する)雇用保険料率」をご確認下さい。
|
1、『 雇用保険料の控除計算が必要となる「従業員」』の確認
給与計算で『 雇用保険料の控除が必要となる「従業員」』は、
| 『「雇用保険の被保険者」である「従業員」』のみとなりますので、この点ご確認下さい。 |
▶ 詳細は『 「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」 』の『 Ⅰ-2:雇用保険料控除の対象となる「従業員の範囲」 』に記載。
2、『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金の範囲」』の確認
|
 「給与支給明細書」等に記載される「給与支給項目」の中には、 「給与支給明細書」等に記載される「給与支給項目」の中には、
・『 雇用保険料の算定基礎となる「給与支給項目」』と
・『 雇用保険料の算定基礎とはならない「給与支給項目」』とがあるため、
 給与計算において「雇用保険料控除額」を計算する場合には、 給与計算において「雇用保険料控除額」を計算する場合には、
『「給与支給明細」に記載されている「給与支給項目」』が、
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」に含めなければならないものであるか否か 』をご確認下さい。
|
▶ 詳細は『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』の『Ⅱ-2(1): 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」につきまして』に記載。
◆ 特にご留意頂きたい事項 ◆
①「源泉所得税の計算」では非課税となる「(非課税)通勤費」や「(非課税)宿直・日直手当」』は、
|
「雇用保険料控除額の計算」におきましては、
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」に含めることが必要となりますので、この点ご注意下さい。
|
② また、「給与支給明細書」に記載される「給与支給額」とは別に、
『「定期券等の支給、社宅等の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』が支給されている場合には、
|
当該「現物給与の支給状況」等によっては、
「現物給与」を金銭評価額して、『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」に含めることが必要となる場合がありますので、この点につきましては注意下さい。
|
◆ 「居住の利益」につきまして ◆
「居住の利益(社宅等貸与)」につきましては、「以下の基準」に基づいて『「賃金」に含めるか否か 』が判断されます。
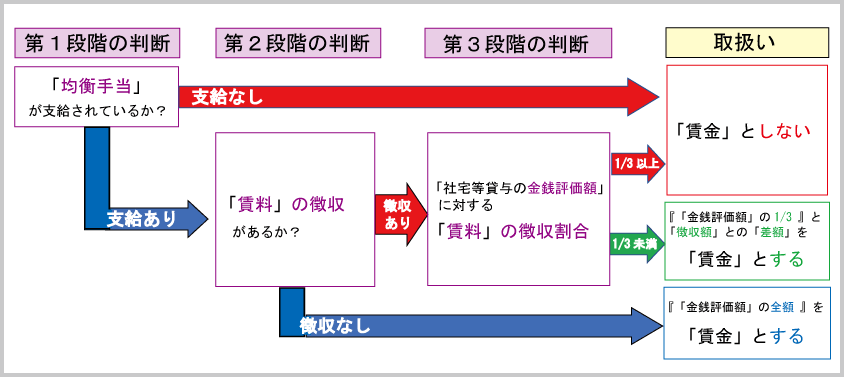
▶ 詳細は『 労働保険制度における「現物給与」の取扱い 』の『 Ⅰ:「社宅等の貸与による利益(居住の利益)」の取扱い 』に記載。
◆ 「食事の利益」につきまして ◆
「食事の利益(食事の提供)」につきましては、「以下の基準」に基づいて『「賃金」に含めるか否か 』が判断されます。
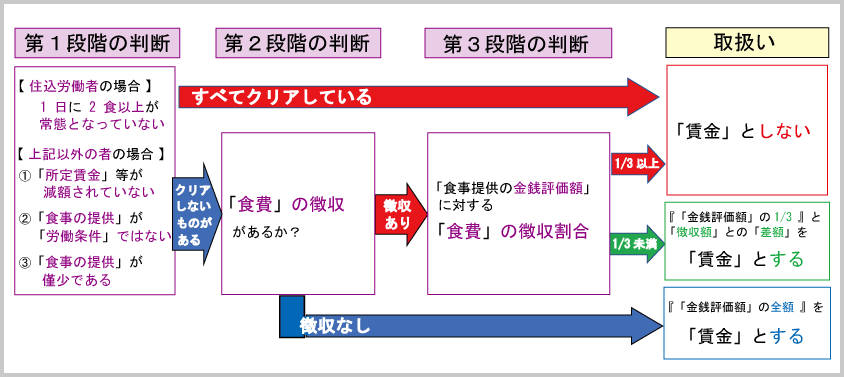
▶ 詳細は『 労働保険制度における「現物給与」の取扱い 』の『 Ⅲ:「「食事の供与による利益(食事の利益)」の取扱い 』に記載。
◆ 「被服の利益」につきまして ◆
「被服の利益(被服の提供等)」につきましては、「以下の基準」に基づいて『「賃金」に含めるか否か 』が判断されます。
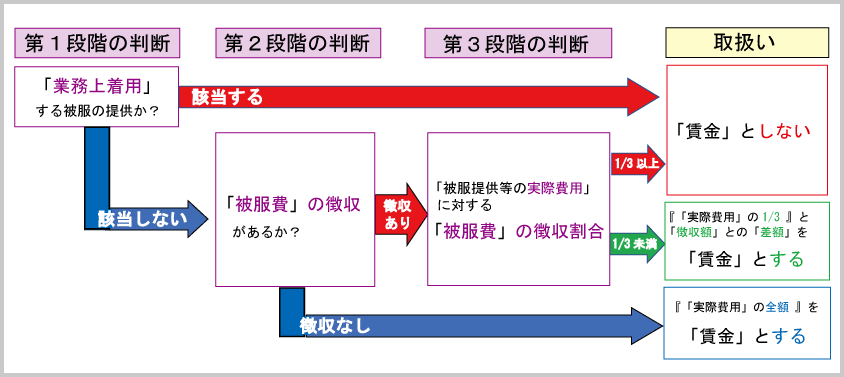
▶ 詳細は『 労働保険制度における「現物給与」の取扱い 』の『 Ⅳ:「被服の提供等による利益(被服の利益)」の取扱い 』に記載。
3、「従業員が負担する雇用保険料率」の確認
 給与計算において「雇用保険料控除額」を計算する場合には、
給与計算において「雇用保険料控除額」を計算する場合には、
| 「従業員が負担する雇用保険料率」を事前にご確認下さい。 |
 なお、『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』は、会社が営む事業の種類ごとに以下の率となります。
なお、『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』は、会社が営む事業の種類ごとに以下の率となります。
【 令和5年保険年度 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)】
| 会社が営む事業の種類 |
従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」 |
| 一般の事業 |
0.006(0.6%) |
農林水産の事業
清酒製造の事業 |
0.007(0.7%) |
| 建設の事業 |
0.007(0.7%) |
▶ 詳細は『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』の『Ⅱ-2(2):『従業員が負担する「雇用保険料率」につきまして』に記載。
◆ 特にご留意頂きたい事項 ◆
①「その労働保険年度の雇用保険料率」は、
| 「 その年の4月分の給与計算」から「 翌年の3月分の給与計算」で控除する雇用保険料の計算に使用します。 |
②「雇用保険料率」は、
|
 毎年「4月分の給与計算で使用する雇用保険料率」から変更される可能性がありますので、 毎年「4月分の給与計算で使用する雇用保険料率」から変更される可能性がありますので、
 「4月分の給与計算」を行う場合には、 「4月分の給与計算」を行う場合には、
「 厚生労働省のHP 」で『「雇用保険料率」が改正されていないか 』をご確認頂ますようお願い致します。
|
Ⅱ:給与計算で『「控除する雇用保険料額」の計算式 』
給与計算で『「控除する雇用保険料額」の計算式 』は、以下のものとなります。
| 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」 × 従業員が負担する雇用保険料率 |
◆ 計算結果の端数処理 ◆
・上記の計算の結果、「1円未満の端数」が生じた場合には、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上は切り上げることとなります。
・なお、上記とは別に、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合には、当該特約に従って処理することとなります。
Ⅲ:「雇用保険料控除額」の具体的な算定例示
ここでは、「具体的な例示」を使用して、『「給与計算で控除する雇用保険料額」の算定方法 』をご紹介させて頂きます。
なお、
 例示1では、令和5年3月分の給与計算において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示1では、令和5年3月分の給与計算において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
 例示2では、令和5年4月分の給与計算において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示2では、令和5年4月分の給与計算において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
 例示3では、「社宅の貸与」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示3では、「社宅の貸与」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
 例示4では、「食事の提供」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示4では、「食事の提供」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
 例示5では、「被服の提供」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示5では、「被服の提供」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
それぞれご紹介させて頂きます。
例 示 1
『 令和5年3月分の給与計算で「控除する雇用保険料額」を算定する場合 』の例示は以下のものとなります。
◆ 設 例 ◆
小売業を営む会社における、R5年3月分の「給与支給状況」が以下のような場合を想定します。
(なお、以下の従業員につきましては、すべて「雇用保険の被保険者」であるとします。)
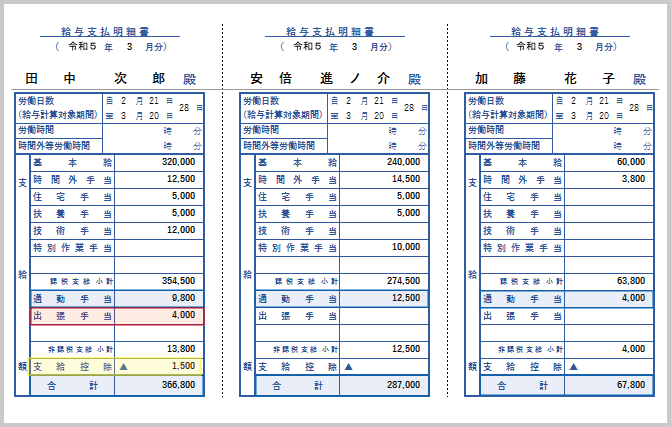
※ 「田中次郎の支給控除(1,500円)」は、「早退があったことによる給与支給額の減額」である。
◆ 「 雇用保険料控除額 」の算定 ◆
1、「控除対象となる被保険者」の確認
上記全員が「雇用保険の被保険者」であることから、
「給与計算」におきましては、上記全員から「(従業員負担分の)雇用保険料」を控除することが必要となります。
2、『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』の計算
 田中次郎 :給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 = 362,800円 田中次郎 :給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 = 362,800円 |
※「出張手当」は「会社費用の実費弁済的な支給」であるため、『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』には含めません。
※ 所得税計算では非課税となる「通勤手当」も、雇用保険料控除額計算では『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めます。
 安倍進ノ介 :給与支給額:287,000円 安倍進ノ介 :給与支給額:287,000円 |
※ 所得税計算では非課税となる「通勤手当」も、雇用保険料控除額計算では『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めます。
 加藤花子 :給与支給額:67,800円 加藤花子 :給与支給額:67,800円 |
※ 所得税計算では非課税となる「通勤手当」も、雇用保険料控除額計算では『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めます。
3、「従業員が負担する雇用保険料率」の確認
| 令和4年度後半(R4年10月~R5年3月)の『「一般の事業」に係る(従業員負担の)雇用保険料率 』は「 0.005 」である。 |
4、「雇用保険料控除額」の算定
|
 田中次郎 :362,800円 × 0.005(一般の事業の保険料率) =1,814円 田中次郎 :362,800円 × 0.005(一般の事業の保険料率) =1,814円
 安倍進ノ介 :287,000円 × 0.005(一般の事業の保険料率) =1,435円 安倍進ノ介 :287,000円 × 0.005(一般の事業の保険料率) =1,435円
 山田花子 :67,800円 × 0.005(一般の事業の保険料率) =339円 山田花子 :67,800円 × 0.005(一般の事業の保険料率) =339円
|
例 示 2
『 令和5年4月分の給与計算で「控除する雇用保険料額」を算定する場合 』の例示は以下のものとなります。
◆ 設 例 ◆
小売業を営む会社における、R5年4月分の「給与支給状況」が以下のような場合を想定します。
(なお、以下の従業員につきましては、すべて「雇用保険の被保険者」であるとします。)
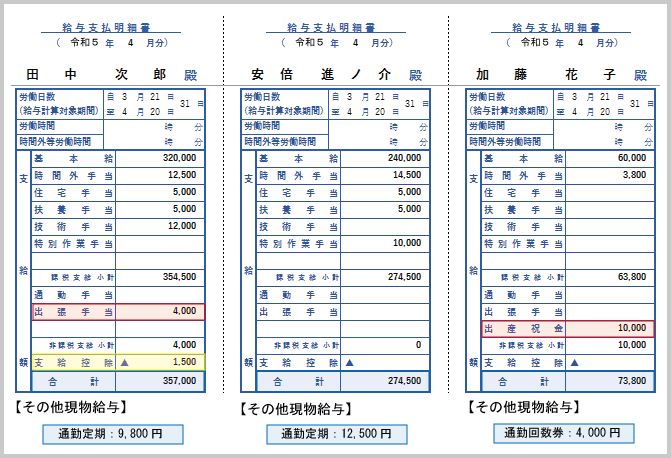
※ 「田中次郎の支給控除(1,500円)」は、「早退があったことによる給与支給額の減額」である。
※「各従業員に支給している通勤定期・通勤回数券」は、「1ヶ月分の通勤定期・通勤回数券」である。
◆ 「 雇用保険料控除額 」の算定 ◆
1、「控除対象となる被保険者」の確認
上記全員が「雇用保険の被保険者」であることから、
「給与計算」におきましては、上記全員から「(従業員負担分の)雇用保険料」を控除することが必要となります。
2、『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』の計算
 田中次郎 : 給与支給額:357,000円 - 出張手当:4,000円 + 通勤定期代:9,800円 = 362,800円 田中次郎 : 給与支給額:357,000円 - 出張手当:4,000円 + 通勤定期代:9,800円 = 362,800円 |
※「出張手当」は「会社費用となるものの実費弁済的な支給」であるため、『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』には含めません。
※ 現物で支給された「通勤定期券」は、「その実際費用額」を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めます。
 安倍進ノ介 :給与支給額:274,500円 + 通勤定期代:12,500円 = 287,000円 安倍進ノ介 :給与支給額:274,500円 + 通勤定期代:12,500円 = 287,000円 |
※ 現物で支給された「通勤定期券」は、「その実際費用額」を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めます。
 加藤花子 :給与支給額:73,800円 - 出産祝金:10,000円 + 通勤回数券:4,000円 = 67,800円 加藤花子 :給与支給額:73,800円 - 出産祝金:10,000円 + 通勤回数券:4,000円 = 67,800円 |
※「出産祝金」は「恩恵的に支給されたもの」であることから、『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』には含めません。
※ 現物で支給された「通勤回数券」は、「その実際費用額」を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めます。
3、「従業員が負担する雇用保険料率」の確認
| 令和5年度(R5年4月~R6年3月)の『「一般の事業」に係る(従業員負担の)雇用保険料率 』は「 0.006 」である。 |
4、「雇用保険料控除額」の算定
|
 田中次郎 :362,800円 × 0.006(一般の事業の保険料率) =2,176.8円 ⇒ 2,177円(50銭以上切上げ) 田中次郎 :362,800円 × 0.006(一般の事業の保険料率) =2,176.8円 ⇒ 2,177円(50銭以上切上げ)
 安倍進ノ介 :287,000円 × 0.006(一般の事業の保険料率) =1,722円 安倍進ノ介 :287,000円 × 0.006(一般の事業の保険料率) =1,722円
 山田花子 :67,800円 × 0.006(一般の事業の保険料率) =406.8円 ⇒ 407円(50銭以上切上げ) 山田花子 :67,800円 × 0.006(一般の事業の保険料率) =406.8円 ⇒ 407円(50銭以上切上げ)
|
例 示 3 :「社宅の貸与」が行われている場合
◆ 設 例 ◆
・以下の従業員(勤務地:東京)に対して「社宅の貸与」が行われていると仮定します。
・なお、会社が営む事業は、建設業であると仮定します。
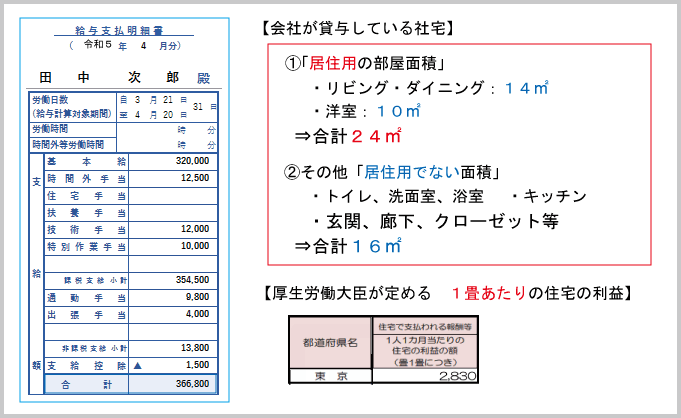
※ 「支給控除(1,500円)」は、「早退があったことによる給与支給額の減額」である。
◆ 社宅の貸与状況 ◆
ケース1
「社宅を貸与している従業員」と「社宅を貸与していない従業員」との均衡を図るための「均衡手当」は支給されていない。
ケース2
「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当」が「20,000円」支給されている。
 2-1:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」として「10,000円」を徴収している。
2-1:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」として「10,000円」を徴収している。
 2-2:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」として「5,000円」を徴収している。
2-2:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」として「5,000円」を徴収している。
 2-3:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」は徴収していない。
2-3:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」は徴収していない。
ケース3
「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当」が「45,000円」支給されている。
 3-1:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料として15,000円」を徴収している。
3-1:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料として15,000円」を徴収している。
 3-2:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料として10,000円」を徴収している。
3-2:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料として10,000円」を徴収している。
 3-3:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」は徴収していない。
3-3:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」は徴収していない。
◆ 「 雇用保険料控除額 」の算定 ◆
ケース1の場合
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
|
「社宅を貸与していない従業員」に対して、「均衡手当」が支給されていない場合には、
『(社宅貸与に係る)現物給与」』を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となります。
|
 このため、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
このため、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 = 362,800円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 362,800円 × 0.007(建設業の保険料率) = 2,540円(端数切上げ)となります。 |
ケース2の場合
 「居住の利益」の金銭評価額
「居住の利益」の金銭評価額
 『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』の計算
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』の計算
| 住居用の部屋面積:24㎡ ÷ 1.65㎡ × 1畳あたりの利益額:2,830円 = 41,163円 (円未満切捨) |
 『「居住の利益」の金銭評価額 』の算定
『「居住の利益」の金銭評価額 』の算定
|
・『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』と「均衡手当」との比較の結果、
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』:41,163円 > 「均衡手当」:20,000円 となるため、
・『「居住の利益」の金銭評価額 』は「 20,000円 」となります。(以下「居住の利益額」とします。)
|
 ケ ー ス 2 – 1
ケ ー ス 2 – 1
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
|
「 10,000円(従業員からの徴収額)」 > 「 20,000円(居住の利益額)× 1/3 = 6,666円 」であるため、
「(社宅貸与に係る)現物給与」を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となります。
|
 このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 = 362,800円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 362,800円 × 0.007(建設業の保険料率) = 2,540円(端数切上げ)となります。 |
 ケ ー ス 2 – 2
ケ ー ス 2 – 2
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
|
・「 5,000円(従業員からの徴収額)」 < 「 20,000円(居住の利益額)× 1/3 = 6,666円 」であるため、
・『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に
「 6,666円 - 5,000円 = 1,666円 」を「(社宅貸与に係る)現物給与」として含めることが必要となります。
|
 このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 + 社宅貸与に係る現物給与:1,666円 = 364,466円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 364,466円 × 0.007(建設業の保険料率) = 2,551円(端数切捨て)となります。 |
 ケ ー ス 2 – 3
ケ ー ス 2 – 3
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
|
・「社宅を貸与している従業員」から「賃料」を徴収していないため、
・『「居住の利益額」の全額 』である「20,000円」を
「(社宅貸与に係る)現物給与」として『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります。
|
 このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 + 社宅貸与に係る現物給与:20,000円 = 382,800円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 382,800円 × 0.007(建設業の保険料率) = 2,680円(端数切上げ)となります。 |
ケース3の場合
 「居住の利益」の金銭評価額
「居住の利益」の金銭評価額
 『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』の計算
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』の計算
| 住居用の部屋面積:24㎡ ÷ 1.65㎡ × 1畳あたりの利益額:2,830円 = 41,163円 (円未満切捨) |
 『「居住の利益」の金銭評価額 』の算定
『「居住の利益」の金銭評価額 』の算定
|
・『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』と「均衡手当」との比較の結果、
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』:41,163円 < 「均衡手当」:45,000円 となるため、
・『「居住の利益」の金銭評価額 』は「 41,163円 」となります。(以下「居住の利益額」とします。)
|
 ケ ー ス 3 – 1
ケ ー ス 3 – 1
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
|
「 15,000円(従業員からの徴収額)」 > 「 41,163円(居住の利益額)× 1/3 = 13,721円 」であるため、
「(社宅貸与に係る)現物給与」を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となります。
|
 このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 = 362,800円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 362,800円 × 0.007(建設業の保険料率) = 2,540円(端数切上げ)となります。 |
 ケ ー ス 3 – 2
ケ ー ス 3 – 2
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
|
・「 10,000円(従業員からの徴収額)」 > 「 41,163円(居住の利益額)× 1/3 = 13,721円 」であるため、
・『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に
「 13,721円 - 10,000円 = 3,721円 」を「(社宅貸与に係る)現物給与」として含めることが必要となります。
|
 このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 + 社宅貸与に係る現物給与:3,721円 = 366,521円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 366,521円 × 0.007(建設業の保険料率) = 2,566円(端数切上げ)となります。 |
 ケ ー ス 3 – 3
ケ ー ス 3 – 3
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
|
・「社宅を貸与している従業員」から「賃料」を徴収していないため、
・『「居住の利益額」の全額 』である「41,163円」を
「(社宅貸与に係る)現物給与」として『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります。
|
 このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
このため、上記従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 + 社宅貸与に係る現物給与:41,163円 = 403,963円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 403,963円 × 0.007(建設業の保険料率) = 2,828円(端数切上げ)となります。 |
例 示 4 :「食事の提供」が行われている場合
◆ 設 例 ◆
・以下の従業員(勤務地:東京)に対して「食事の提供」が行われていると仮定します。
・なお、会社が営む事業は、サービス業であると仮定します。
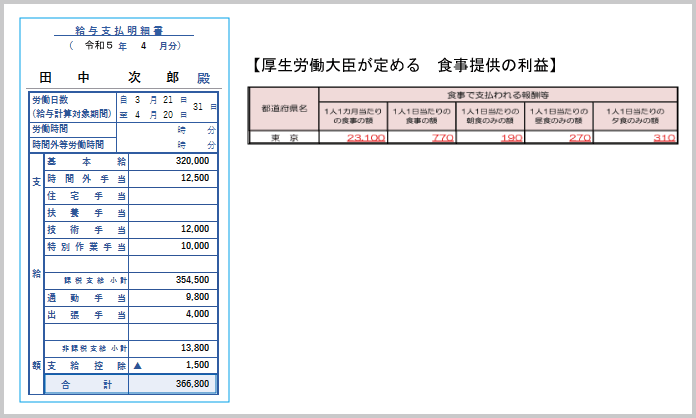
※ 「支給控除(1,500円)」は、「早退があったことによる給与支給額の減額」である。
◆ 食事の提供状況 ◆
ケース1
・当月において、昼食を20日提供し、
・当該従業員から「食事代」として1食につき「300円」を徴収している。
ケース2
・当月において、昼食を22日提供し、
・当該従業員から「食事代」として1食につき「50円」を徴収している。
ケース3
・当月において、昼食を18日提供し、
・当該従業員から「食事代」は徴収していない。
◆ 「 雇用保険料控除額 」の算定 ◆
ケース1
 『「食事の利益」の金銭評価額 』の算定
『「食事の利益」の金銭評価額 』の算定
|
・『 厚生労働大臣が定める「食事提供の利益額」』は、
昼食提供回数:20回 × 昼食1食あたりの利益額:270円 = 5,400円 となるため、
・『「食事の利益」の金銭評価額 』は「 5,400円 」となります。(以下、「食事の利益額」とします。)
|
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(食事提供に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(食事提供に係る)現物給与」
|
・「 20回 × 300円 = 6,000円(徴収額)」 > 「 5,400円(食事の利益額)× 1/3 = 1,666円 」であるため、
・「(食事提供に係る)現物給与」を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となります。
|
 上記の結果、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
上記の結果、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 = 362,800円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 362,800円 × 0.006(一般の事業の保険料率) = 2,177円(端数切上げ) となります。 |
ケース2
 『「食事の利益」の金銭評価額 』の算定
『「食事の利益」の金銭評価額 』の算定
|
・『 厚生労働大臣が定める「食事提供の利益額」』は、
昼食提供回数:22回 × 昼食1食あたりの利益額:270円 = 5,940円 となるため、
・『「食事の利益」の金銭評価額 』は「 5,940円 」となります。(以下、「食事の利益額」とします。)
|
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(食事提供に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(食事提供に係る)現物給与」
|
・「 22回 × 50円 = 1,100円(徴収額)」 < 「 5,940円(食事の利益額)× 1/3 = 1,980円 」であるため、
・「 1,980円(食事の利益額の1/3の金額) - 1,100円(徴収額) = 880円 」を
「(食事提供に係る)現物給与」として『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります。
|
 上記の結果、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
上記の結果、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 + 食事提供に係る現物給与:880円 = 363,680円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 363,680円 × 0.006(一般の事業の保険料率) = 2,182円(端数切捨て) となります。 |
ケース3
 『「食事の利益」の金銭評価額 』の算定
『「食事の利益」の金銭評価額 』の算定
|
・『 厚生労働大臣が定める「食事提供の利益額」』は、
昼食提供回数:18回 × 昼食1食あたりの利益額:270円 = 4,860円 となるため、
・『「食事の利益」の金銭評価額 』は「 4,860円 」となります。(以下、「食事の利益額」とします。)
|
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(食事提供に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(食事提供に係る)現物給与」
|
・「食事を提供している従業員」から「食費」の徴収はないことから、
・『「(食事提供に係る)現物給与」の 全額 』である「 4,860円 」を
「(食事提供に係る)現物給与」として『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります。
|
 上記の結果、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
上記の結果、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 + 食事提供に係る現物給与:4,860円 = 367,660円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 367,660円 × 0.006(一般の事業の保険料率) = 2,206円(端数切上げ) となります。 |
例 示 5 :「制服の提供」が行われている場合
◆ 設 例 ◆
・以下の従業員(勤務地:東京)に対して「制服の提供」が行われていると仮定します。
・なお、会社が営む事業は、製造業であると仮定します。
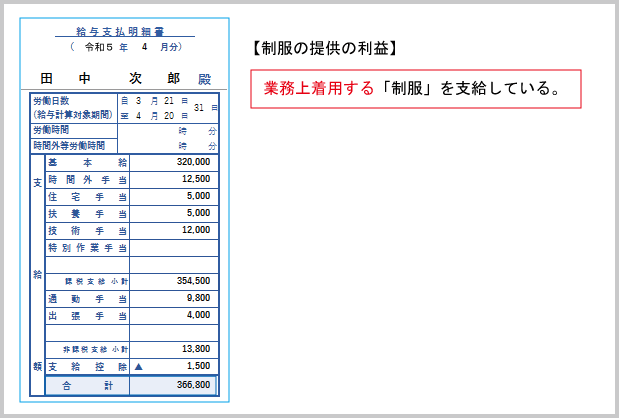
※ 「支給控除(1,500円)」は、「早退があったことによる給与支給額の減額」である。
◆ 「 雇用保険料控除額 」の算定 ◆
 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含める「(社宅貸与に係る)現物給与」
|
「業務上着用することを条件」に会社から「被服の提供」が行われている場合には、
『(被服提供に係る)現物給与」』を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となります。
|
 このため、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
このため、当該従業員の『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
| 給与支給額:366,800円 - 出張手当:4,000円 = 362,800円 となり、 |
 当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
当該従業員の給与計算において「控除する雇用保険料」は、
| 362,800円 × 0.006(一般の事業の保険料率) = 2,177円(端数切上げ)となります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは『 給与計算で控除する「雇用保険料の具体的な計算方法」』につき、ご紹介させて頂いております。
 なお、当該ページでは、例示を用いて『 給与計算において「控除する雇用保険料額」の具体的な算定方法 』をご紹介することがメインとなりますので、
なお、当該ページでは、例示を用いて『 給与計算において「控除する雇用保険料額」の具体的な算定方法 』をご紹介することがメインとなりますので、
『「雇用保険料控除額の算定方法」の背景にある事項 』につきましては、以下のページをご参照頂きますようお願い致します。
・『「雇用保険料の控除額計算」に関する基礎的事項 』のご紹介 ⇒ 「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」
・『 雇用保険料額の算定基礎となる「賃金」』についてのご紹介 ⇒ 労働保険料の算定基礎となる「賃金の範囲」
・ 労働保険制度における『「現物給与」の取扱い 』のご紹介 ⇒ 労働保険制度における「現物給与」の取扱い
・『 厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」』の算定方法 ⇒ 厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」
「控除雇用保険料額の算定方法」につきまして
 給与計算において「控除する雇用保険料額」を算定すること自体は、
給与計算において「控除する雇用保険料額」を算定すること自体は、
比較的簡単に算定することができるため、是非この機会に算定方法をマスターして頂きますようお願い致します。
 ただし、「社宅の貸与、食事の提供、被服の貸与・提供」などの「現物給与」が支給されている場合には、
ただし、「社宅の貸与、食事の提供、被服の貸与・提供」などの「現物給与」が支給されている場合には、
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』を把握する場合に、少々厄介な計算が必要となりますので、
「上記Ⅲの例示3、4、5等で記載させて頂きました算定方法」をご確認頂ますようお願い致します。
「雇用保険料率」の改正につきまして
『 上記Ⅰ-3「特にご留意頂きたい事項」』でご紹介させて頂いておりますように、
「4月分の給与計算」を行う場合には、『 雇用保険料控除額の算定基礎率である「雇用保険料率」』が改正される可能性がありますので、
「4月分の給与計算」を行う場合には、『「雇用保険料率」の改正がなされているか否か 』のご確認をして頂きますようお願い致します。
![]() 給与計算において「雇用保険料控除額」を計算する場合には、
給与計算において「雇用保険料控除額」を計算する場合には、![]() なお、『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』は、会社が営む事業の種類ごとに以下の率となります。
なお、『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』は、会社が営む事業の種類ごとに以下の率となります。![]() 例示1では、令和5年3月分の給与計算において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示1では、令和5年3月分の給与計算において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、![]() 例示2では、令和5年4月分の給与計算において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示2では、令和5年4月分の給与計算において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、![]() 例示3では、「社宅の貸与」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示3では、「社宅の貸与」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、![]() 例示4では、「食事の提供」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示4では、「食事の提供」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、![]() 例示5では、「被服の提供」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、
例示5では、「被服の提供」が行われている場合において『「従業員給与から控除する雇用保険料額」の算定方法 』を、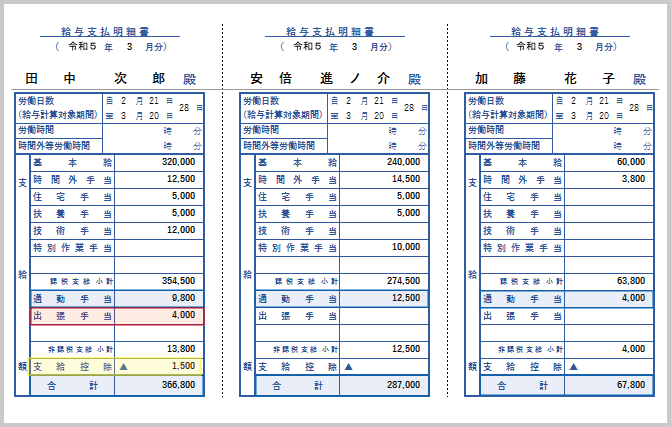
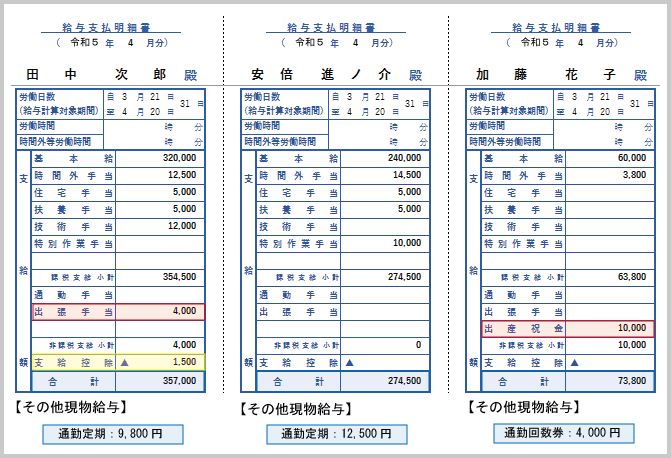
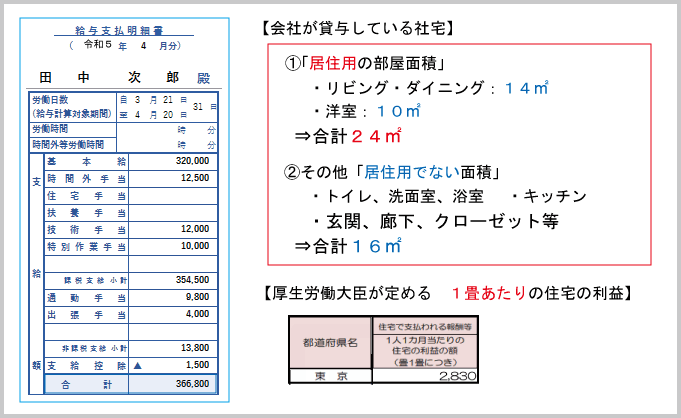
![]() 2-1:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」として「10,000円」を徴収している。
2-1:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」として「10,000円」を徴収している。![]() 2-2:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」として「5,000円」を徴収している。
2-2:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」として「5,000円」を徴収している。![]() 2-3:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」は徴収していない。
2-3:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」は徴収していない。![]() 3-1:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料として15,000円」を徴収している。
3-1:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料として15,000円」を徴収している。![]() 3-2:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料として10,000円」を徴収している。
3-2:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料として10,000円」を徴収している。![]() 3-3:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」は徴収していない。
3-3:上記とともに、「社宅を貸与している従業員」から「社宅の賃料」は徴収していない。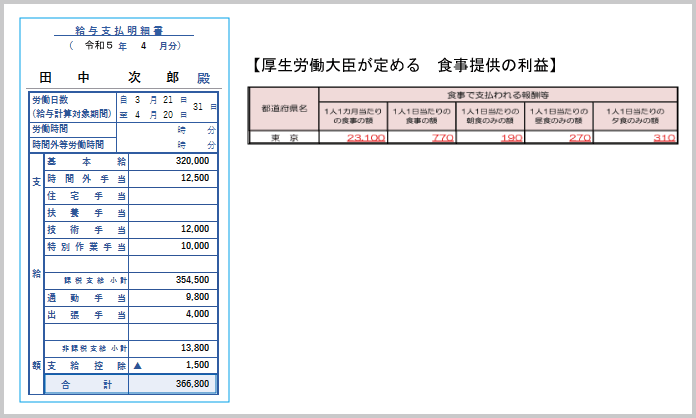
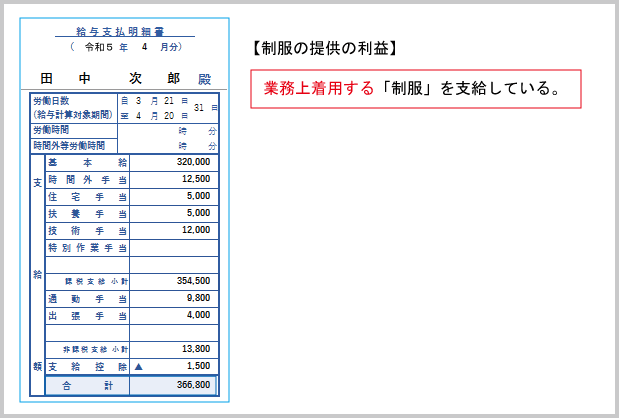
![]() なお、当該ページでは、例示を用いて『 給与計算において「控除する雇用保険料額」の具体的な算定方法 』をご紹介することがメインとなりますので、
なお、当該ページでは、例示を用いて『 給与計算において「控除する雇用保険料額」の具体的な算定方法 』をご紹介することがメインとなりますので、![]() 給与計算において「控除する雇用保険料額」を算定すること自体は、
給与計算において「控除する雇用保険料額」を算定すること自体は、![]() ただし、「社宅の貸与、食事の提供、被服の貸与・提供」などの「現物給与」が支給されている場合には、
ただし、「社宅の貸与、食事の提供、被服の貸与・提供」などの「現物給与」が支給されている場合には、