ここでは、労働保険制度における『「現物給与」の取り扱い 』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページは『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』及び『 労働保険料の算定基礎となる「賃金の範囲」 』というページを補完するものとなります。
▶ 労働保険制度における『「現物給与」の基本的な取扱い 』
 『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』には、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』には、
 『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、
『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、
|
・これら「現物給与」が『「労働の対償」として支給されている 』と認められる場合には、
・これら「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 他方、『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、
他方、『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、
|
「過去からの慣行」として、
会社から従業員に対して『「福利厚生目的」のために支給されてきた 』という経緯もあることから、
|
 「労働保険制度」では、このことを考慮し、
「労働保険制度」では、このことを考慮し、
|
『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」等の「現物給与」』が、
・『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、
・それらを『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないとする規定も設けています。
|
 以上のように、「労働保険制度」におきましては、
以上のように、「労働保険制度」におきましては、
|
『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』は、
 それらが『「「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、 それらが『「「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、
・それら「現物給与」は『「労働の対償」として支給されているものではない 』と考え、
・『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めない取扱いをし、
 それらが『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と認められる場合には、 それらが『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と認められる場合には、
・それら「現物給与」は『「労働の対償」として支給されているものである 』と考え、
・『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含める取扱いをし、
それらが支給される状況等によって、「異なる取扱い」をする規定を設けています。
|
 このため、ここでは、
このため、ここでは、
 「住居(社宅等)の貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅰ で、
「住居(社宅等)の貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅰ で、
 『「住居(社宅等)の貸与」に伴う「水道光熱費の会社負担」』についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅱ で、
『「住居(社宅等)の貸与」に伴う「水道光熱費の会社負担」』についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅱ で、
 「食事の提供」という「現物給与」の労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅲ で、
「食事の提供」という「現物給与」の労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅲ で、
 「被服の提供・貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅳ でご紹介させて頂きます。
「被服の提供・貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅳ でご紹介させて頂きます。
 なお、ここでご紹介させて頂きます規定は、あくまで「労働保険制度」に限定した取扱規定となるものであり、
なお、ここでご紹介させて頂きます規定は、あくまで「労働保険制度」に限定した取扱規定となるものであり、
- 従業員等の個人所得税の課税対象となる『「給与(課税支給額)」の範囲 』や
- 社会保険料の「標準報酬月額」算定における『「報酬(報酬月額)」の範囲 』につきましては、
「それぞれの制度」で「それぞれ別の取扱い」がなされていますので、この点につきましてはご留意下さい。
Ⅰ:「社宅等の貸与による利益(居住の利益)」の取扱い
1、「社宅等の貸与」の取扱概要
 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
|
「労働保険制度」におきましては、
 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、
その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となりますが、
 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と認められる場合には、 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と認められる場合には、
その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります。
|
 この点、「社宅・寮等の貸与(社宅等の貸与)」におきましては、
この点、「社宅・寮等の貸与(社宅等の貸与)」におきましては、
|
「社宅等の貸与」が、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合の「判断基準」を設け、
|
|
 「社宅等の貸与」が当該「判断基準」に該当する場合には、 「社宅等の貸与」が当該「判断基準」に該当する場合には、
(すなわち、「社宅等の貸与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と判断されれば、)
当該「社宅等の貸与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となりますが、
 「社宅等の貸与」が当該「判断基準」に該当しない場合には、 「社宅等の貸与」が当該「判断基準」に該当しない場合には、
(すなわち、「社宅等の貸与」が『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と判断されれば、)
当該「社宅等の貸与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 なお、「上記の判断基準」につきましては、
なお、「上記の判断基準」につきましては、
|
 「第1段階の判断基準」として、 「第1段階の判断基準」として、
|
「社宅等を貸与していない従業員」に対して、
「社宅等を貸与している従業員」との均衡を図るための「均衡手当」が支給されているか
|
 「第2段階の判断基準」として、 「第2段階の判断基準」として、
| 「社宅等を貸与している従業員」から「(社宅等の使用料である)賃料」を会社が徴収しているか |
 「第3段階の判断基準」として、 「第3段階の判断基準」として、
| 「社宅等を貸与している従業員」から会社が『「賃料」をどの程度 』徴収しているか |
の「判断基準」が設けられています。
|
2、「社宅等の貸与」の具体的な取扱い
上記1)では『「取扱い」の概要 』をご紹介させて頂きましたが、
「社宅等の貸与」に関する『 労働保険制度上での「具体的な取扱い」』は以下のものとなります。
◆ 「第1段階の基準」による判断 ◆
 まず「 最初の判断 」として、
まず「 最初の判断 」として、
|
|
会社から「社宅等を貸与していない従業員」に対して、
「社宅等を貸与している従業員」との均衡を図るための「均衡手当」が支給されているかを基準として、
|
「社宅等の貸与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)会社から「社宅等を貸与していない従業員」に対して、「均衡手当」が支払われていない場合には、
|
・当該「社宅等の貸与」は 『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と見做されるため、
・当該「社宅等の貸与」につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります。
|
ⅱ) 他方、会社から「社宅等を貸与していない従業員」に対して、「均衡手当」が支払われている場合には、
|
・当該「社宅等の貸与」は、この段階では『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』とは認められず、
・当該状況下で支給されている「社宅等の貸与」につきましては、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第2段階の判断」が行われます。
|
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 「社宅等の貸与」は、
「社宅等の貸与」は、
| 過去からの慣行として、『「会社の福利厚生施策」として従業員に支給されてきた 』という経緯があることから、 |
「労働保険制度」では、
|
・当該「社宅等の貸与」は、基本的に『「福利厚生目的の範囲」で支給されているもの 』と考え、
・これを、原則『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いをしています。
|
 ただし、「社宅等を貸与していない従業員」に対して「均衡手当」が支給されているような場合は、
ただし、「社宅等を貸与していない従業員」に対して「均衡手当」が支給されているような場合は、
|
( この「均衡手当」が『「労働の対償」として支給されているもの 』として扱われることから、)
これに対応する「社宅等の貸与」も『「労働の対償」として支給されているものである 』という面を持つことになります。
|
このため、このような場合には、
|
・『「社宅等の貸与」が「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』につき、この段階で結論を下すことは一旦保留し、
・「別の基準」により、再度『 それが「福利厚生目的の範囲」で支給されているかを判断する 』こととしています。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
◆ 「第2段階の基準」による判断 ◆
 「 第2段階の判断 」としては、
「 第2段階の判断 」としては、
『 上記「第1段階」では「福利厚生目的の範囲で支給されているとは判断されなかったもの」』に対して、
|
| 「社宅等を貸与している従業員」から「(社宅等の使用料である)賃料」を徴収しているかを基準として、 |
再度、「社宅等の貸与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)会社が「社宅等を貸与している従業員」から、「賃料(使用料)」を徴収していない場合には、
|
・当該『 賃料の徴収がない「社宅等の貸与」』は 『「労働の対償」として支給されている 』と見做されるため、
・当該『 賃料の徴収がない「社宅等の貸与」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 なお、この場合には『「社宅等貸与の全体」が「労働の対償」として支給されている 』と考えるため、
なお、この場合には『「社宅等貸与の全体」が「労働の対償」として支給されている 』と考えるため、
|
『「社宅等貸与の金銭評価額」※の全額 』を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
ⅱ) 他方、会社が「社宅等を貸与している従業員」から、「賃料(使用料)」を徴収している場合には、
|
・当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』は 『「福利厚生目的」のために支給されている 』と判断されるため、
・当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても
|
・『 従業員から徴収する「賃料」』があまりにも僅少である場合には、
当該「社宅等の貸与」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、
・ 当該状況下で支給されている「社宅等の貸与」につきましては、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第3段階の判断」が行われます。
|
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 「労働保険制度」におきましては、
「労働保険制度」におきましては、
|
 「社宅等を貸与していない従業員」に「均衡手当」が支給されている場合で、 「社宅等を貸与していない従業員」に「均衡手当」が支給されている場合で、
 かつ『 会社が「社宅等を貸与している従業員」から「社宅等貸与の賃料」を徴収していない 』場合には、 かつ『 会社が「社宅等を貸与している従業員」から「社宅等貸与の賃料」を徴収していない 』場合には、
 当該『 賃料の徴収がない「社宅等の貸与」』は、 当該『 賃料の徴収がない「社宅等の貸与」』は、
(「均衡手当」と同じく)『「労働の対償」として支給されているもの 』と考えるため、
 当該『 賃料の徴収がない「社宅等の貸与」』につきましては、 当該『 賃料の徴収がない「社宅等の貸与」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めるという取扱いがなされます。
|
 なお、この場合には『「社宅等貸与の全体」が「労働の対償」として支給されている 』と考えるため、
なお、この場合には『「社宅等貸与の全体」が「労働の対償」として支給されている 』と考えるため、
|
『「社宅等貸与の金銭評価額」※の全額 』を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 他方、
他方、
|
 「社宅等を貸与していない従業員」に「均衡手当」が支給されている場合であっても、 「社宅等を貸与していない従業員」に「均衡手当」が支給されている場合であっても、
 『「社宅等を貸与している従業員」から「社宅等の貸与に係る賃料」を徴収している 』という行為がある場合には、 『「社宅等を貸与している従業員」から「社宅等の貸与に係る賃料」を徴収している 』という行為がある場合には、
 当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』は、 当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』は、
『 会社が「福利厚生目的」で行う「居住費用の部分的な支援行為」』であると考えるため、
 当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』につきましては、 当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても
|
・『 従業員から徴収する「賃料」』があまりにも僅少である場合には、
当該「社宅等の貸与」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、
・当該状況下で支給されている「社宅等の貸与」につきましては、
「社宅等を貸与している従業員」から『「どの程度の賃料」を徴収しているか 』を基準として、
「社宅等貸与」に『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている部分がないか 』を再度判断することになります。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
「取扱方法」が記載されている規定
『「賃金」に含める金額 』が記載されている規定
|
50403 により賃金の範囲とされた現物給与の評価額は、次による。
イ 法令又は労働協約に評価額が定められているときは当該評価額
ロ 食事、被服及び住居の利益以外のもので法令又は労働協約に支払の範囲のみが定められ、評価額の定めがない場合は、安定所長が当該事業所の所在地区の市場価格を基準として評価した額
ハ 食事、被服及び住居の利益については、法令又は労働協約に評価額が定められていないときは、健康保険法第 46 条の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた評価額を参考として安定所長が評価した額
この場合において、安定所の管轄区域内であっても、例えば、都市地区とその他の地区との物価、家屋の賃貸価格等に著しい差があること等一律の額をもって評価することが不適当であるときは、地区別に評価額を定めることが望ましい。
また、住居を無償で供与される場合において、住居の利益を得ない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない均衡手当が支給されるときは、住居の貸与の利益が明確に評価されているものであるから、当該額を限度として評価する。
( 雇用保険に関する業務取扱要領 50404(4)現物給与の評価 )
|
◆ 「第3段階の基準」による判断 ◆
 「 第3段階の判断 」としては、
「 第3段階の判断 」としては、
『 上記「第2段階」では『「原則、福利厚生目的のために支給されていると判断されたもの」 』に対して、
|
| 「社宅等を貸与している従業員」から「どの程度の賃料」を徴収しているかを基準として、 |
再度、「社宅等の貸与」が「福利厚生目的の範囲で支給されているか」の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)『 従業員から徴収する「賃料」』が、『「社宅等貸与の金銭評価額」※の1/3 以上の金額 』である場合には、
|
・当該『 1/3以上の賃料徴収を伴う「社宅等の貸与」』は 、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と見做されるため、
・当該『 1/3以上の賃料徴収を伴う「社宅等の貸与」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります。
|
ⅱ) 他方、『 従業員から徴収する「賃料」』が、『「社宅等貸与の金銭評価額」※の1/3 未満の金額 』である場合には、
|
 『「社宅等貸与の金銭評価額※の1/3 の金額」と「賃料徴収額」との「差額部分」』は、 『「社宅等貸与の金銭評価額※の1/3 の金額」と「賃料徴収額」との「差額部分」』は、
労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されたものである 』と見做されるため、
 当該『「社宅等貸与の金銭評価額※の1/3 の金額」から「賃料徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、 当該『「社宅等貸与の金銭評価額※の1/3 の金額」から「賃料徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
◆ 「社宅等貸与の金銭評価額」につきまして (上記※につきまして) ◆
 「社宅等の貸与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」に含めるかの判断 』を行う場合には、
「社宅等の貸与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」に含めるかの判断 』を行う場合には、
|
 上記「第2段階の判断」における 上記「第2段階の判断」における
『「労働保険料の算定基礎となる賃金」に含める「社宅等貸与の金額」』を算定する場合や
 上記「第3段階の判断」における 上記「第3段階の判断」における
『「社宅等の貸与」を「労働保険料の算定基礎となる賃金」に含めるか否かの判断 』を行う場合や、
 上記「第3段階の判断」における 上記「第3段階の判断」における
『「労働保険料の算定基礎となる賃金」に含める「社宅等貸与の金額」』を算定する場合に、
「社宅等貸与の金銭評価額」という概念を使用することになるため、
これらの場面におきましては、「社宅等貸与の金銭評価額」を適切に把握することが必要となりますが、
|
 この「社宅等貸与の金銭評価額」は、
この「社宅等貸与の金銭評価額」は、
|
 『「社宅等を貸与していない従業員」に支給される「均衡手当」』と 『「社宅等を貸与していない従業員」に支給される「均衡手当」』と
 『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の価額」に基づいて「算定した金額」』のうちの、 『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の価額」に基づいて「算定した金額」』のうちの、
いずれか「小さい方の金額」となります。
|
 従いまして、「社宅等貸与の金銭評価額」を把握する場合には、
従いまして、「社宅等貸与の金銭評価額」を把握する場合には、
|
 『「社宅等を貸与していない従業員」に支給される「均衡手当」』を把握するとともに、 『「社宅等を貸与していない従業員」に支給される「均衡手当」』を把握するとともに、
 『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の価額」に従って算定した「社宅等貸与の評価額」』を把握し、 『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の価額」に従って算定した「社宅等貸与の評価額」』を把握し、
『 両者のうちの「いずれか小さい金額」』を『「社宅等貸与の金銭評価額」として採用することが必要となりますので、
この点につきましては、ご留意頂きますようお願い致します。
|
▶ 『 厚生労働大臣が定める「社宅貸与の価額」』につきましては、「 日本年金機構のHP 」にて公表されておりますので、
「社宅等貸与の金銭評価額」を把握する必要がある場合には、上記リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
▶ また、『 厚生労働大臣が定める「社宅貸与の価額」』につきましては、別途『厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」』において、その算定方法等を記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧下さい。
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 「労働保険制度」におきましては、
「労働保険制度」におきましては、
|
 「社宅等を貸与していない従業員」に「均衡手当」が支給されている場合であっても、 「社宅等を貸与していない従業員」に「均衡手当」が支給されている場合であっても、
 『「社宅等を貸与している従業員」から「社宅等の貸与に係る賃料」を徴収している 』という行為がある場合には、 『「社宅等を貸与している従業員」から「社宅等の貸与に係る賃料」を徴収している 』という行為がある場合には、
 当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』は、 当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』は、
『 会社が「福利厚生目的」で行う「居住費用の部分的な支援行為」』であると考えるため、
 当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』につきましては、 当該『 賃料の徴収を伴う「社宅等の貸与」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、『 従業員から徴収する「賃料」』があまりにも僅少である場合には、
ただし、『 従業員から徴収する「賃料」』があまりにも僅少である場合には、
| 当該「社宅等貸与」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考える部分 』が含まれるため、 |
 『 従業員から徴収している「賃料」』が『「社宅等貸与の金銭評価額」※の1/3 未満 』であるような僅少な場合には、
『 従業員から徴収している「賃料」』が『「社宅等貸与の金銭評価額」※の1/3 未満 』であるような僅少な場合には、
|
 『「社宅等貸与の金銭評価額※の1/3 の金額」と「賃料徴収額」との「差額部分」』は、 『「社宅等貸与の金銭評価額※の1/3 の金額」と「賃料徴収額」との「差額部分」』は、
労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されたものである 』と見做され、
 当該『「社宅等貸与の金銭評価額※の1/3 の金額」から「賃料徴収額」を「差し引いた金額」』は、 当該『「社宅等貸与の金銭評価額※の1/3 の金額」から「賃料徴収額」を「差し引いた金額」』は、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めて取扱うことが必要となります。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
◆ 『「社宅等の貸与」の取扱い 』のまとめ ◆
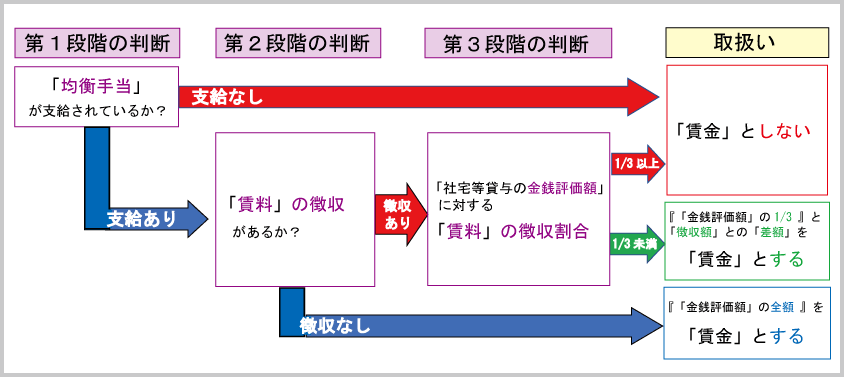
3、『「社宅等の貸与」の取扱い 』についての「例示」によるご紹介
1)「均衡手当」が支給されていない場合
例示
| 「社宅の貸与」を行っているが、これに伴う「均衡手当」の支給はない。 |
取扱い
|
当該「社宅の貸与」につきましては、
・「社宅を貸与していない従業員」へ「均衡手当」が支給されていないため、
・『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります。
|
2)「均衡手当」が支給されている場合
①「賃料」の徴収がない場合
例示
|
 「社宅の貸与」を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当」を支給している。 「社宅の貸与」を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当」を支給している。
 また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料」は徴収していない。 また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料」は徴収していない。
 なお、「均衡手当の支給額」は4万円であり、『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」』は5万円である。 なお、「均衡手当の支給額」は4万円であり、『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」』は5万円である。
|
取扱い
|
当該「社宅の貸与」につきましては、
・「社宅を貸与していない従業員」へ「均衡手当」が支給されており、
・「社宅を貸与している従業員」から「賃料」を徴収していないため、
 『「社宅貸与の金銭評価額」の全額 』を 『「社宅貸与の金銭評価額」の全額 』を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
なお、「社宅貸与の金銭評価額」は、
|
「均衡手当の支給額」である「 4万円 」となるため、
( 「均衡手当の支給額(4万円)」<『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」(5万円)』 )
|
結果、
| 「 4万円 」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。 |
②「賃料」の徴収がある場合
ⅰ)「賃料の徴収金額」が『「社宅貸与の金銭評価額」の1/3以上 』である場合
例示
|
 「社宅の貸与」を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当」を支給している。 「社宅の貸与」を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当」を支給している。
 また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料」として1万円を徴収している。 また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料」として1万円を徴収している。
 なお、「均衡手当の支給額」は4万円であり、『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」』は3万円である。 なお、「均衡手当の支給額」は4万円であり、『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」』は3万円である。
|
取扱い
|
当該「社宅の貸与」につきましては、
・「社宅を貸与していない従業員」へ「均衡手当」が支給されているが、
・「社宅を貸与している従業員」から「賃料」を徴収しており、
「その賃料徴収額(1万円)」は『「社宅貸与の金銭評価額(3万円)」の1/3以上 』であるため、
 当該『 1/3以上の賃料徴収を伴う「社宅の貸与」』につきましては、 当該『 1/3以上の賃料徴収を伴う「社宅の貸与」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります。
|
なお、上記における「社宅貸与の金銭評価額」は、
|
『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」』である「 3万円 」となります。
( 『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」(3万円)』<「均衡手当の支給額(4万円)」
|
ⅱ)「賃料の徴収金額」が『「社宅貸与の金銭評価額」の1/3未満 』である場合
例示
|
 「社宅の貸与」を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当」を支給している。 「社宅の貸与」を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当」を支給している。
 また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料」として4千円を徴収している。 また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料」として4千円を徴収している。
 なお、「均衡手当の支給額」は3万円であり、『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」』は4万円である。 なお、「均衡手当の支給額」は3万円であり、『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」』は4万円である。
|
取扱い
|
当該「社宅の貸与」につきましては、
・「社宅を貸与していない従業員」へ「均衡手当」が支給されており、
・「社宅を貸与している従業員」から「賃料」を徴収しているが、
「その賃料徴収額(4千円)」は『「社宅貸与の金銭評価額(3万円)」の1/3未満 』であるため、
 当該『 1/3未満の賃料徴収を伴う「社宅の貸与」』につきましては、 当該『 1/3未満の賃料徴収を伴う「社宅の貸与」』につきましては、
『「社宅貸与の金銭評価額の1/3 の金額」と「賃料徴収額」との「差額部分」』を、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
なお、「社宅貸与の金銭評価額」は、
|
「均衡手当の支給額」である「 3万円 」となるため、
( 「均衡手当の支給額(3万円)」<『 厚生労働大臣が定めた「社宅貸与の評価額」(4万円) 』)
|
結果、
|
「 6千円 」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
( 『「社宅等貸与の金銭評価額(3万円)」× 1/3 』-「賃料徴収額(4千円)」= 6千円 )
|
▶ なお、『「社宅等の貸与」の取扱い 』についての「具体的例示」つきましては、
『 「雇用保険料控除額」の具体的な計算方法 』の『 Ⅲ:「雇用保険料控除額」の具体的な算定例示 例示3 』でもご紹介をしておりますので、必要となる場合には、当該ページもご覧頂きますようお願い致します。
Ⅱ:『「社宅等の水道光熱費」の会社負担 』の取扱い
「社宅等の貸与」が行われている下で、『 社宅等で従業員が使用した「水道光熱費」』を会社が負担している場合には、
|
 『 会社が負担した「水道光熱費」』は、 『 会社が負担した「水道光熱費」』は、
『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている「現物給付」』であると考えられるため、
 『 会社が負担した「水道光熱費」にかかる「実際費用の全額」』につきましては、 『 会社が負担した「水道光熱費」にかかる「実際費用の全額」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 労働保険制度上、「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないとされるのは、
労働保険制度上、「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないとされるのは、
| その「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められることがその理由とされますが、 |
 『 社宅等において従業員が使用した「水道光熱費」』を会社が負担しているような場合には、
『 社宅等において従業員が使用した「水道光熱費」』を会社が負担しているような場合には、
|
当該『 会社が負担している「水道光熱費」』は、
「過去からの慣行」や「社会通念上行われている福利厚生施策」を考えても、
『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている「現物給付」』であると考えられます。
|
 このため『 社宅等において従業員が使用した「水道光熱費」』を会社が負担するような場合には、
このため『 社宅等において従業員が使用した「水道光熱費」』を会社が負担するような場合には、
|
 当該『「会社が負担している水道光熱費」の全体 』が、 当該『「会社が負担している水道光熱費」の全体 』が、
労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されたものである 』と見做されるため、
 当該『「会社が負担している水道光熱費」にかかる「実際費用の全額」』を、 当該『「会社が負担している水道光熱費」にかかる「実際費用の全額」』を、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めて取扱うことが必要となります。
|
Ⅲ:「食事の供与による利益(食事の利益)」の取扱い
1、「食事の提供」の取扱概要
 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
|
「労働保険制度」におきましては、
 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、
その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となりますが、
 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と認められる場合には、 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と認められる場合には、
その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります。
|
 この点、「食事の提供」におきましては、
この点、「食事の提供」におきましては、
|
「食事の提供」が、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合の「判断基準」を設け、
|
|
 「食事の提供」が当該「判断基準」に該当する場合には、 「食事の提供」が当該「判断基準」に該当する場合には、
(すなわち、「食事の提供」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と判断されれば、)
当該「食事の提供」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となりますが、
 「食事の提供」が当該「判断基準」に該当しない場合には、 「食事の提供」が当該「判断基準」に該当しない場合には、
(すなわち、「食事の提供」が『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と判断されれば、)
当該「食事の提供」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 なお、「上記の判断基準」につきましては、
なお、「上記の判断基準」につきましては、
|
 「第1段階の判断基準」として、 「第1段階の判断基準」として、
|
・『「住込労働者」に対する「食事提供」』の場合には、
1 日に 2 食以上給食されることが「常態になっていないか」
・『「上記以外の者」に対する「食事提供」』の場合には、
①「食事の提供」を条件として『「所定賃金」等が減額されていないか 』
②「食事を提供する」ことが労働協約・就業規則に定められるなど『「明確な労働条件の内容」となっていないか 』
③「食事提供の客観的評価額」が『「社会通念上僅少なもの」であるか 』
|
 「第2段階の判断基準」として、 「第2段階の判断基準」として、
| 「食事を提供している従業員」から「食費」を会社が徴収しているか |
 「第3段階の判断基準」として、 「第3段階の判断基準」として、
| 「食事を提供している従業員」から会社が『「食費」をどの程度 』徴収しているか |
の「判断基準」が設けられています。
|
2、「食事の提供」の具体的な取扱い
上記1)では『「取扱い」の概要 』をご紹介させて頂きましたが、
「食事の提供」に関する『 労働保険制度上での「具体的な取扱い」』は以下のものとなります。
◆ 「第1段階の基準」による判断 ◆
 まず「 最初の判断 」として、
まず「 最初の判断 」として、
|
|
1)「住込労働者」に対する「食事提供」の場合には、
1 日に 2 食以上給食されることが常態となっていない
2)「上記以外の者」に対する「食事提供」の場合には、
①「食事の提供」を条件として「所定賃金」等が減額されていない
②「食事を提供する」ことが、労働協約・就業規則に定められるなど「明確な労働条件の内容」となっていない
③「食事提供の客観的評価額」が「社会通念上僅少なもの」である
ということをを「基準」として、
|
「食事の提供」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)「 上記(1)の事項 」 又は 「 上記(2)①~③のすべての事項 」をクリアしている場合には、
|
・当該「食事の提供」は 『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と見做されるため、
・当該「食事の提供」を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります。
|
ⅱ) 他方、「 上記(1)の事項 」 又は 「 上記(2)①~③のいずれかの事項 」をクリアしない場合には、
|
・当該「食事の提供」は、この段階では『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』とは認められず、
・当該状況下で支給されている「食事の提供」につきましては、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第2段階の判断」が行われます。
|
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 「食事の提供」は、
「食事の提供」は、
| 過去からの慣行として、『「会社の福利厚生施策」として従業員に支給されてきた 』という経緯があることから、 |
 「労働保険制度」では、
「労働保険制度」では、
|
1)「住込労働者に対する「食事提供」において、
『 1 日に 2 食以上給食されることが常態となっていない 』場合には、
2)「上記以外の者」に対する「食事提供」において、
・『「食事の提供」を条件として「所定賃金」等が減額されておらず 』
・ かつ、『「食事を提供する」ことが、労働協約・就業規則に定められるなど「明確な労働条件の内容」となっておらず 』
・ かつ、『「食事提供の客観的評価額」が「社会通念上僅少なもの」である 』ような場合には、
|
当該「食事の提供」は、
|
・『「福利厚生目的の範囲」で支給されているもの 』と看做し、
・これを、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いをしています。
|
 他方、
他方、
|
1)「住込労働者に対する「食事提供」において、
『 1 日に 2 食以上給食されることが常態となっている 』ような場合
2)「上記以外の者」に対する「食事提供」において、
・『「食事の提供」を条件として「所定賃金」等が減額されている 』又は、
・『「食事を提供する」ことが、労働協約・就業規則に定められるなど「明確な労働条件の内容」となっている 』又は、
・『「食事提供の客観的評価額」が「社会通念上僅少なもの」ではない 』ような場合には、
|
当該「食事の提供」は、
|
 その「食事の提供頻度」や「食事提供にかかる金額」などを考慮すると、 その「食事の提供頻度」や「食事提供にかかる金額」などを考慮すると、
『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』という面を持ったり、
 その「食事の提供条件」や「食事の提供状況」などを考慮すると、 その「食事の提供条件」や「食事の提供状況」などを考慮すると、
『「労働の対償」として支給されている 』という面を持つことになります。
|
 このため、このような場合には、
このため、このような場合には、
|
・『「食事の提供」が「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』につき、この段階で結論を下すことは一旦保留し、
・「別の基準」を加味し、再度『 それが「福利厚生目的の範囲」で支給されているかを判断する 』こととしています。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
|
食事の利益は、賃金とされる。
ただし、食事の提供に対して、その実費相当額が賃金から減額されるもの及びたまたま支給される食事等、福利厚生的なものと認められるものは賃金日額の算定の基礎に算入しない。
なお、食事の利益(住込労働者で 1 日に 2 食以上給食されることが常態にある場合を除く。) については、原則として、次のすべてに該当する場合は、賃金として取り扱わず、福利厚生的なものとして取り扱う。
(イ) 給食によって賃金の減額を伴わないこと
(ロ) 労働協約、就業規則に定められるなど、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと
(ハ) 給食による客観的評価額が社会通念上僅少なものと認められる場合であること
また、乗船中の船員に対する「食料の支給」は、海上労働者の特殊性から船舶所有者に課せられた義務であり(船員法第 80 条)、労務の対償として支払われるものでないことから、賃金として取り扱わない。
( 雇用保険に関する業務取扱要領 50501(1)賃金と解されるものの例 ヨ 食事の利益 )
|
◆ 「第2段階の基準」による判断 ◆
 「 第2段階の判断 」としては、
「 第2段階の判断 」としては、
『 上記「第1段階」では「福利厚生目的の範囲で支給されているとは判断されなかったもの」』に対して、
|
| 「食事を提供している従業員」から「食費」を徴収しているかを基準として、 |
再度、「食事の提供」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)会社が「食事を提供している従業員」から、「食費」を徴収していない場合には、
|
・当該『 食費の徴収がない「食事の提供」』は、
『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と見做されるため、
・当該『 食費の徴収がない「食事の提供」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 なお、この場合には、
なお、この場合には、
『「食事提供」の全体 』が『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と考えるため、
|
『「食事提供の金銭評価額」※の全額 』を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
ⅱ) 他方、会社が「食事を提供している従業員」から、「食費」を徴収している場合には、
|
・当該『 食費の徴収を伴う「食費の提供」』は 『「福利厚生目的」のために支給されている 』と判断されるため、
・当該『 食費の徴収を伴う「食費の提供」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても
|
・『 従業員から徴収する「食費」』があまりにも僅少である場合には、
当該「食事の提供」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、
・ 当該状況下で支給されている「食事の提供」につきましては、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第3段階の判断」が行われます。
|
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 「労働保険制度」におきましては、
「労働保険制度」におきましては、
|
 「食事の提供」が『「労働の対償としての性格」や「福利厚生目的の範囲を超えるような性格」』を持つ場合で、 「食事の提供」が『「労働の対償としての性格」や「福利厚生目的の範囲を超えるような性格」』を持つ場合で、
 かつ『 会社が「食事を提供している従業員」から「食事提供にかかる食費」を徴収していない 』場合には、 かつ『 会社が「食事を提供している従業員」から「食事提供にかかる食費」を徴収していない 』場合には、
 当該『 食費の徴収がない「食事の提供」』は、 当該『 食費の徴収がない「食事の提供」』は、
『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されているもの 』と考えるため、
 当該『 食費の徴収がない「食事の提供」』につきましては、 当該『 食費の徴収がない「食事の提供」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めるという取扱いがなされます。
|
 なお、この場合には、
なお、この場合には、
『「食事提供」の全体 』が『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と考えるため、
|
『「食事提供の金銭評価額」※の全額 』を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 他方、
他方、
|
 「食事の提供」が『「労働の対償としての性格」や「福利厚生目的の範囲を超えるような性格」』を持つ場合であっても、 「食事の提供」が『「労働の対償としての性格」や「福利厚生目的の範囲を超えるような性格」』を持つ場合であっても、
 『「食事を提供している従業員」から「食事提供にかかる食費」を徴収している 』という行為がある場合には、 『「食事を提供している従業員」から「食事提供にかかる食費」を徴収している 』という行為がある場合には、
 当該『 食費の徴収を伴う「食事の提供」』は、 当該『 食費の徴収を伴う「食事の提供」』は、
『 会社が「福利厚生目的」で行う「食事費用の部分的な支援行為」』であると考えるため、
 当該『 食費の徴収を伴う「食事の提供」』につきましては、 当該『 食費の徴収を伴う「食事の提供」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても
|
・『 従業員から徴収する「食費」』があまりにも僅少である場合には、
当該「食事の提供」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、
・当該状況下で支給されている「食事の提供」につきましては、
「食事を提供している従業員」から『「どの程度の食費」を徴収しているか 』を基準として、
「食事の提供」に『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている部分がないか 』を再度判断することになります。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
「取扱方法」が記載されている規定
『「賃金」に含める金額 』が記載されている規定
|
50403 により賃金の範囲とされた現物給与の評価額は、次による。
イ 法令又は労働協約に評価額が定められているときは当該評価額
ロ 食事、被服及び住居の利益以外のもので法令又は労働協約に支払の範囲のみが定められ、評価額の定めがない場合は、安定所長が当該事業所の所在地区の市場価格を基準として評価した額
ハ 食事、被服及び住居の利益については、法令又は労働協約に評価額が定められていないときは、健康保険法第 46 条の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた評価額を参考として安定所長が評価した額
この場合において、安定所の管轄区域内であっても、例えば、都市地区とその他の地区との物価、家屋の賃貸価格等に著しい差があること等一律の額をもって評価することが不適当であるときは、地区別に評価額を定めることが望ましい。
また、住居を無償で供与される場合において、住居の利益を得ない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない均衡手当が支給されるときは、住居の貸与の利益が明確に評価されているものであるから、当該額を限度として評価する。
( 雇用保険に関する業務取扱要領 50404(4)現物給与の評価 )
|
◆ 「第3段階の基準」による判断 ◆
 「 第3段階の判断 」としては、
「 第3段階の判断 」としては、
『 上記「第2段階」では『「原則、福利厚生目的のために支給されていると判断されたもの」 』に対して、
|
| 「食事を提供している従業員」から「どの程度の食費」を徴収しているかを基準として、 |
再度、「食事の提供」が「福利厚生目的の範囲で支給されているか」の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)『 従業員から徴収する「食費」』が、『「食事提供の金銭評価額」※の1/3 以上の金額 』である場合には、
|
・当該『 1/3以上の食費徴収を伴う「食事の提供」』は 、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と見做されるため、
・当該『 1/3以上の食費徴収を伴う「食事の提供」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります。
|
ⅱ) 他方、『 従業員から徴収する「食費」』が、『「食事提供の金銭評価額」※の1/3 未満の金額 』である場合には、
|
 『「食事提供の金銭評価額※の1/3 の金額」と「食費徴収額」との「差額部分」』は、 『「食事提供の金銭評価額※の1/3 の金額」と「食費徴収額」との「差額部分」』は、
労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されたものである 』と見做されるため、
 当該『「食事提供の金銭評価額※の1/3 の金額」から「食費徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、 当該『「食事提供の金銭評価額※の1/3 の金額」から「食費徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
◆ 「食事提供の金銭評価額」につきまして (上記※につきまして) ◆
 「食事の提供」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」に含めるかの判断 』を行う場合には、
「食事の提供」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」に含めるかの判断 』を行う場合には、
|
 上記「第2段階の判断」における 上記「第2段階の判断」における
『「労働保険料の算定基礎となる賃金」に含める「食事提供の金額」』を算定する場合や
 上記「第3段階の判断」における 上記「第3段階の判断」における
『「食事の提供」を「労働保険料の算定基礎となる賃金」に含めるか否かの判断 』を行う場合や、
 上記「第3段階の判断」における 上記「第3段階の判断」における
『「労働保険料の算定基礎となる賃金」に含める「食事提供の金額」』を算定する場合に、
「食事提供の金銭評価額」という概念を使用することになるため、
これらの場面におきましては、「食事提供の金銭評価額」を適切に把握することが必要となりますが、
|
 この「食事提供の金銭評価額」は、
この「食事提供の金銭評価額」は、
| 『 厚生労働大臣が定めた「食事提供の価額」に基づいて「算定した金額」』となります。 |
 従いまして、「食事提供の金銭評価額」を把握する場合には、
従いまして、「食事提供の金銭評価額」を把握する場合には、
|
『 厚生労働大臣が定めた「食事提供の価額」』に従って、「食事提供の金銭評価額」を算定することが必要となりますので、
この点につきましては、ご留意頂きますようお願い致します。
|
▶ 『 厚生労働大臣が定める「食事の価額」』につきましては、「 日本年金機構のHP 」にて公表されておりますので、
「食事提供の金銭評価額」を把握する必要がある場合には、上記リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
▶ また、『 厚生労働大臣が定める「食事提供の価額」』につきましては、別途『厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」』において、その算定方法等を記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧下さい。
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 「労働保険制度」におきましては、
「労働保険制度」におきましては、
|
 「食事の提供」が『「労働の対償としての性格」や「福利厚生目的の範囲を超えるような性格」』を持つ場合であっても、 「食事の提供」が『「労働の対償としての性格」や「福利厚生目的の範囲を超えるような性格」』を持つ場合であっても、
 『「食事を提供している従業員」から「食事の提供にかかる食費」を徴収している 』という行為がある場合には、 『「食事を提供している従業員」から「食事の提供にかかる食費」を徴収している 』という行為がある場合には、
 当該『 食費の徴収を伴う「食事の提供」』は、 当該『 食費の徴収を伴う「食事の提供」』は、
『 会社が「福利厚生目的」で行う「食事費用の部分的な支援行為」』であると考えるため、
 当該『 食費の徴収を伴う「食事の提供」』につきましては、 当該『 食費の徴収を伴う「食事の提供」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、『 従業員から徴収する「食費」』があまりにも僅少である場合には、
ただし、『 従業員から徴収する「食費」』があまりにも僅少である場合には、
| 当該「食事提供」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考える部分 』が含まれるため、 |
 『 従業員から徴収している「食費」』が『「食事提供の金銭評価額」※の1/3 未満 』であるような僅少な場合には、
『 従業員から徴収している「食費」』が『「食事提供の金銭評価額」※の1/3 未満 』であるような僅少な場合には、
|
 『「食事提供の金銭評価額※の1/3 の金額」と「食費徴収額」との「差額部分」』は、 『「食事提供の金銭評価額※の1/3 の金額」と「食費徴収額」との「差額部分」』は、
労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されたものである 』と見做され、
 当該『「食事提供の金銭評価額※の1/3 の金額」から「食費徴収額」を「差し引いた金額」』は、 当該『「食事提供の金銭評価額※の1/3 の金額」から「食費徴収額」を「差し引いた金額」』は、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めて取扱うことが必要となります。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
◆ 『「食事の提供」の取扱い 』のまとめ ◆
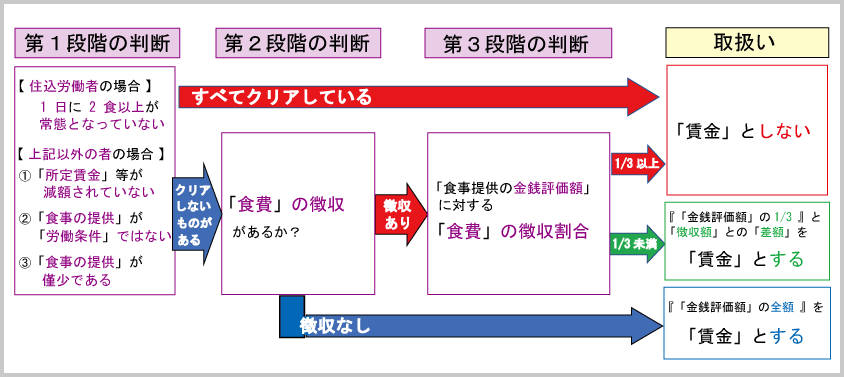
3、『「食事の提供」の取扱い 』についての「例示」によるご紹介
『「食事の提供」の取扱い 』についての「具体的例示」つきましては、
『 「雇用保険料控除額」の具体的な計算方法 』の『 Ⅲ:「雇用保険料控除額」の具体的な算定例示 例示4 』でご紹介をしております。
Ⅳ:「被服の提供等による利益(被服の利益)」の取扱い
1、「被服の提供等」の取扱概要
 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
|
「労働保険制度」におきましては、
 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、
その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となりますが、
 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と認められる場合には、 「現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と認められる場合には、
その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります。
|
 この点、「被服の提供・貸与(被服の提供等)」におきましては、
この点、「被服の提供・貸与(被服の提供等)」におきましては、
|
「被服の提供等」が、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合の「判断基準」を設け、
|
|
 「被服の提供等」が当該「判断基準」に該当する場合には、 「被服の提供等」が当該「判断基準」に該当する場合には、
(すなわち、「被服の提供等」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と判断されれば、)
当該「被服の提供等」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となりますが、
 「被服の提供等」が当該「判断基準」に該当しない場合には、 「被服の提供等」が当該「判断基準」に該当しない場合には、
(すなわち、「被服の提供等」が『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている 』と判断されれば、)
当該「被服の提供等」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 なお、「上記の判断基準」につきましては、
なお、「上記の判断基準」につきましては、
|
 「第1段階の判断基準」として、 「第1段階の判断基準」として、
| 会社から従業員に「提供等されている被服」』が「業務上着用する被服」であるか |
 「第2段階の判断基準」として、 「第2段階の判断基準」として、
| 「被服を提供等している従業員」から「被服費」を会社が徴収しているか |
 「第3段階の判断基準」として、 「第3段階の判断基準」として、
| 「被服を提供等している従業員」から会社が『「被服費」をどの程度 』徴収しているか |
の「判断基準」が設けられています。
|
2、「被服の提供等」の具体的な取扱い
上記1)では『「取扱い」の概要 』をご紹介させて頂きましたが、
「被服の提供等」に関する『 労働保険制度上での「具体的な取扱い」』は以下のものとなります。
◆ 「第1段階の基準」による判断 ◆
 まず「 最初の判断 」として、
まず「 最初の判断 」として、
|
| 『 会社から従業員に「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」であるかを基準として、 |
「被服の提供等」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)『 会社から従業員に「提供等されている被服」』が、「業務上着用するための被服」である場合には、
|
・当該「被服の提供等」は 『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と見做されるため、
・当該「被服の提供等」を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります。
|
ⅱ) 他方、『 会社から従業員に「提供等されている被服」』が、「業務上着用するための被服」でない場合には、
|
・当該「被服の提供等」は、この段階では『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』とは認められず、
・当該状況下で支給されている「被服の提供等」につきましては、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第2段階の判断」が行われます。
|
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 『 業務上着用する「被服の提供等」』は、
『 業務上着用する「被服の提供等」』は、
| 過去からの慣行として、『「会社の福利厚生施策」として従業員に支給されてきた 』という経緯があることから、 |
「労働保険制度」では、
|
・当該『 業務上着用する「被服の提供等」』は『「福利厚生目的の範囲」で支給されているもの 』と考え、
・これを、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いをしています。
|
 他方、『 会社から「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」でない場合は、
他方、『 会社から「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」でない場合は、
|
当該「被服の提供等」は、
『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』という面を持つことになるため、
|
このような場合には、
|
・『「被服の提供等」が「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』につき、この段階で結論を下すことは一旦保留し、
・「別の基準」により、再度『 それが「福利厚生目的の範囲」で支給されているかを判断する 』こととしています。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
◆ 「第2段階の基準」による判断 ◆
 「 第2段階の判断 」としては、
「 第2段階の判断 」としては、
『 上記「第1段階」では「福利厚生目的の範囲で支給されているとは判断されなかったもの」』に対して、
|
| 「被服を提供等している従業員」から「被服費」を徴収しているかを基準として、 |
再度、「被服の提供等」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)会社が「被服を提供等している従業員」から、「被服費」を徴収していない場合には、
|
・当該『 被服費の徴収がない「被服の提供等」』は、
『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と見做されるため、
・当該『 被服費の徴収がない「被服の提供等」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 なお、この場合には、
なお、この場合には、
『「被服提供等」の全体 』が『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と考えるため、
|
『「被服提供等にかかる実際費用」の全額 』を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
ⅱ) 他方、会社が「被服を提供等している従業員」から、「被服費」を徴収している場合には、
|
・当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』は 『「福利厚生目的」のために支給されている 』と判断されるため、
・当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても
|
・『 従業員から徴収する「被服費」』があまりにも僅少である場合には、
当該「被服の提供等」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、
・ 当該状況下で支給されている「被服の提供等」につきましては、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第3段階の判断」が行われます。
|
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 「労働保険制度」におきましては、
「労働保険制度」におきましては、
|
 『 会社から「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」でない場合で、 『 会社から「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」でない場合で、
 かつ『 会社が「被服を提供等している従業員」から「被服提供等の被服費」を徴収していない 』場合には、 かつ『 会社が「被服を提供等している従業員」から「被服提供等の被服費」を徴収していない 』場合には、
 当該『 被服費の徴収がない「被服の提供等」』は、 当該『 被服費の徴収がない「被服の提供等」』は、
『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と考えるため、
 当該『 被服費の徴収がない「被服の提供等」』につきましては、 当該『 被服費の徴収がない「被服の提供等」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めるという取扱いがなされます。
|
 なお、この場合には、
なお、この場合には、
『「被服提供等」の全体 』が『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と考えるため、
|
『「被服提供等にかかる実際費用」の全額 』を
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
 他方、
他方、
|
 『 会社から「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」でない場合であっても、 『 会社から「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」でない場合であっても、
 『「被服を提供等している従業員」から「被服の提供等にかかる被服費」を徴収している 』という行為がある場合には、 『「被服を提供等している従業員」から「被服の提供等にかかる被服費」を徴収している 』という行為がある場合には、
 当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』は、 当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』は、
『 会社が「福利厚生目的」で行う「被服費用の部分的な支援行為」』であると考えるため、
 当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』につきましては、 当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても
|
・『 従業員から徴収する「被服費」』があまりにも僅少である場合には、
当該「被服の提供等」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、
・当該状況下で支給されている「被服の提供等」につきましては、
「被服を提供等している従業員」から『「どの程度の被服費」を徴収しているか 』を基準として、
「被服の提供等」に『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されている部分がないか 』を再度判断することになります。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
◆ 「第3段階の基準」による判断 ◆
 「 第3段階の判断 」としては、
「 第3段階の判断 」としては、
『 上記「第2段階」では『「原則、福利厚生目的のために支給されていると判断されたもの」 』に対して、
|
| 「被服を提供等している従業員」から「どの程度の被服費」を徴収しているかを基準として、 |
再度、「被服の提供等」が「福利厚生目的の範囲で支給されているか」の判断が行われます。
|
 そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、
ⅰ)『 従業員から徴収する「被服費」』が、『「被服提供等の実際費用」の1/3 以上の金額 』である場合には、
|
・当該『 1/3以上の被服費徴収を伴う「被服の提供等」』は 、
『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と見做されるため、
・当該『 1/3以上の被服費徴収を伴う「被服の提供等」』につきましては、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります。
|
ⅱ) 他方、『 従業員から徴収する「被服費」』が、『「被服提供等の実際費用」の1/3 未満の金額 』である場合には、
|
 『「被服提供等の実際費用の1/3 の金額」と「被服費徴収額」との「差額部分」』は、 『「被服提供等の実際費用の1/3 の金額」と「被服費徴収額」との「差額部分」』は、
労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されたものである 』と見做されるため、
 当該『「被服提供等の実際費用の1/3 の金額」から「被服費徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、 当該『「被服提供等の実際費用の1/3 の金額」から「被服費徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります。
|
◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆
 「労働保険制度」におきましては、
「労働保険制度」におきましては、
|
 『 会社から「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」でない場合であっても、 『 会社から「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」でない場合であっても、
 『「被服を提供等している従業員」から「被服の提供等にかかる被服費」を徴収している 』という行為がある場合には、 『「被服を提供等している従業員」から「被服の提供等にかかる被服費」を徴収している 』という行為がある場合には、
 当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』は、 当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』は、
『 会社が「福利厚生目的」で行う「被服費用の部分的な支援行為」』であると考えるため、
 当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』につきましては、 当該『 被服費の徴収を伴う「被服の提供等」』につきましては、
原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。
|
 ただし、『 従業員から徴収する「被服費」』があまりにも僅少である場合には、
ただし、『 従業員から徴収する「被服費」』があまりにも僅少である場合には、
| 当該「被服の提供等」には『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されていると考える部分 』が含まれるため、 |
 『 従業員から徴収している「被服費」』が『「被服提供等の実際費用」の1/3 未満 』であるような僅少な場合には、
『 従業員から徴収している「被服費」』が『「被服提供等の実際費用」の1/3 未満 』であるような僅少な場合には、
|
 『「被服提供等の実際費用の1/3 の金額」と「被服費徴収額」との「差額部分」』は、 『「被服提供等の実際費用の1/3 の金額」と「被服費徴収額」との「差額部分」』は、
労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲」を超えて支給されたものである 』と見做され、
 当該『「被服提供等の実際費用の1/3 の金額」から「被服費徴収額」を「差し引いた金額」』は、 当該『「被服提供等の実際費用の1/3 の金額」から「被服費徴収額」を「差し引いた金額」』は、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めて取扱うことが必要となります。
|
◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆
◆ 『「被服の提供等」の取扱い 』のまとめ ◆
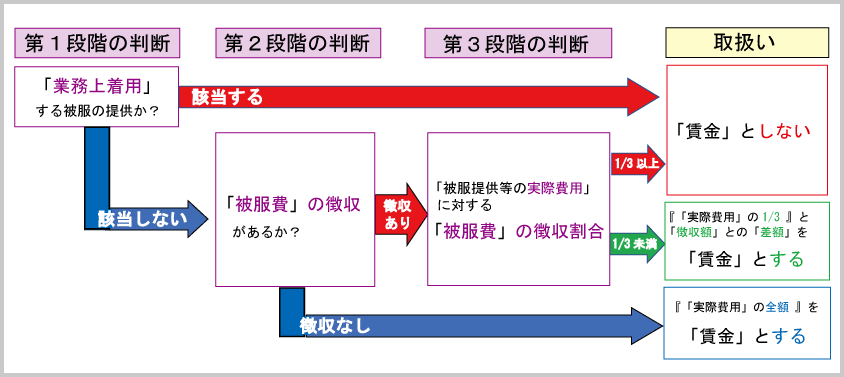
3、『「被服の提供等」の取扱い 』についての「例示」によるご紹介
『「被服の提供等」の取扱い 』についての「具体的例示」つきましては、
『 「雇用保険料控除額」の具体的な計算方法 』の『 Ⅲ:「雇用保険料控除額」の具体的な算定例示 例示5 』でご紹介をしております。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『 労働保険における「現物給与」の取扱い 』についてご紹介させて頂きております。
 会社から従業員等へ「現物給与」が支給されている場合には、
会社から従業員等へ「現物給与」が支給されている場合には、
- 所得税法上での「現物給与の取扱い(課税所得に含まれる否か等の取扱い)」
- 社会保険での「現物給与の取扱い(社会保険制度上「報酬」に含まれるか否か等の取扱い)」
- 労働保険での「現物給与の取扱い(労働保険制度上「賃金」に含まれるか否か等の取扱い)」
が、それぞれ問題となり、かつそれぞれの制度上での取扱いが異なるものとなっています。
 このため、「現物給与」が支給されている場合には、
このため、「現物給与」が支給されている場合には、
- 所得税法上での取扱い
- 社会保険での取扱い
- 労働保険での取扱い
をそれぞれ理解し、確認することが必要となりますので、
 ここでは、本文でご紹介させて頂きました内容をご理解頂き、
ここでは、本文でご紹介させて頂きました内容をご理解頂き、
まずは『 労働保険での「現物給与」の取扱い 』をマスターして頂きますようお願い致します。
![]() 『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』には、
『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』には、![]() 『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、
『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、![]() 他方、『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、
他方、『「居住(社宅等)の貸与、食事の提供、被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、![]() 「労働保険制度」では、このことを考慮し、
「労働保険制度」では、このことを考慮し、![]() 以上のように、「労働保険制度」におきましては、
以上のように、「労働保険制度」におきましては、![]() このため、ここでは、
このため、ここでは、![]() 「住居(社宅等)の貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅰ で、
「住居(社宅等)の貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅰ で、![]() 『「住居(社宅等)の貸与」に伴う「水道光熱費の会社負担」』についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅱ で、
『「住居(社宅等)の貸与」に伴う「水道光熱費の会社負担」』についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅱ で、![]() 「食事の提供」という「現物給与」の労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅲ で、
「食事の提供」という「現物給与」の労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅲ で、![]() 「被服の提供・貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅳ でご紹介させて頂きます。
「被服の提供・貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを 下記Ⅳ でご紹介させて頂きます。![]() なお、ここでご紹介させて頂きます規定は、あくまで「労働保険制度」に限定した取扱規定となるものであり、
なお、ここでご紹介させて頂きます規定は、あくまで「労働保険制度」に限定した取扱規定となるものであり、![]() 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、![]() この点、「社宅・寮等の貸与(社宅等の貸与)」におきましては、
この点、「社宅・寮等の貸与(社宅等の貸与)」におきましては、![]() なお、「上記の判断基準」につきましては、
なお、「上記の判断基準」につきましては、![]() まず「 最初の判断 」として、
まず「 最初の判断 」として、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、![]() 「 第2段階の判断 」としては、
「 第2段階の判断 」としては、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、![]() なお、この場合には『「社宅等貸与の全体」が「労働の対償」として支給されている 』と考えるため、
なお、この場合には『「社宅等貸与の全体」が「労働の対償」として支給されている 』と考えるため、![]() ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても![]() 「 第3段階の判断 」としては、
「 第3段階の判断 」としては、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、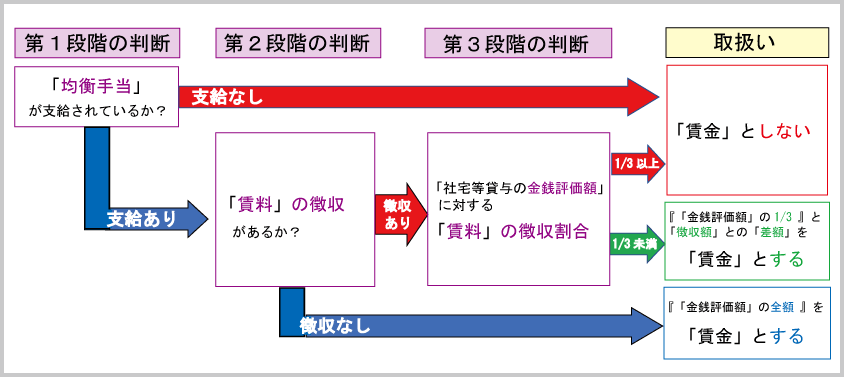
![]() 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、![]() この点、「食事の提供」におきましては、
この点、「食事の提供」におきましては、![]() なお、「上記の判断基準」につきましては、
なお、「上記の判断基準」につきましては、![]() まず「 最初の判断 」として、
まず「 最初の判断 」として、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、![]() 「 第2段階の判断 」としては、
「 第2段階の判断 」としては、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、![]() なお、この場合には、
なお、この場合には、![]() ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても![]() 「 第3段階の判断 」としては、
「 第3段階の判断 」としては、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、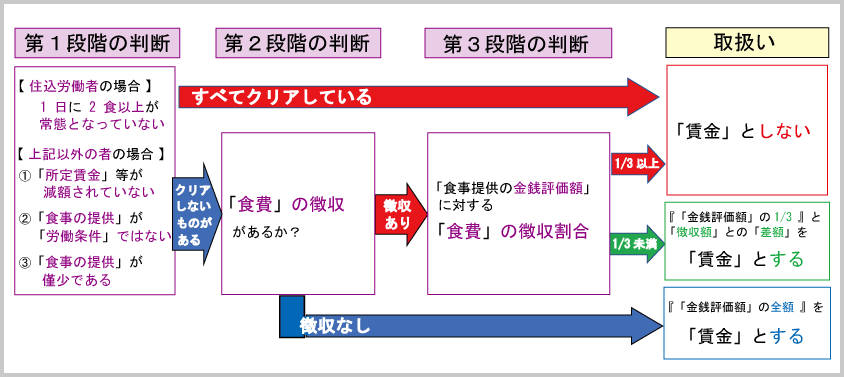
![]() 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、![]() この点、「被服の提供・貸与(被服の提供等)」におきましては、
この点、「被服の提供・貸与(被服の提供等)」におきましては、![]() なお、「上記の判断基準」につきましては、
なお、「上記の判断基準」につきましては、![]() まず「 最初の判断 」として、
まず「 最初の判断 」として、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、![]() 「 第2段階の判断 」としては、
「 第2段階の判断 」としては、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、![]() なお、この場合には、
なお、この場合には、![]() ただし、この場合であっても
ただし、この場合であっても![]() 「 第3段階の判断 」としては、
「 第3段階の判断 」としては、![]() そして、上記「判断」の結果、
そして、上記「判断」の結果、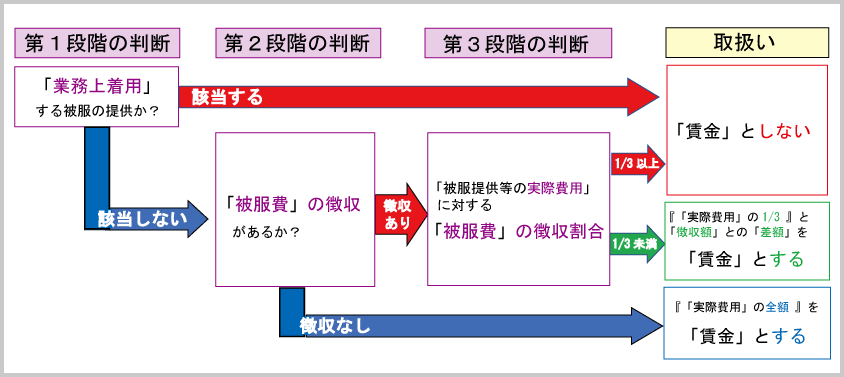
![]() 会社から従業員等へ「現物給与」が支給されている場合には、
会社から従業員等へ「現物給与」が支給されている場合には、![]() このため、「現物給与」が支給されている場合には、
このため、「現物給与」が支給されている場合には、![]() ここでは、本文でご紹介させて頂きました内容をご理解頂き、
ここでは、本文でご紹介させて頂きました内容をご理解頂き、