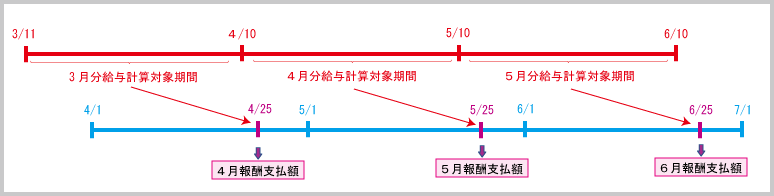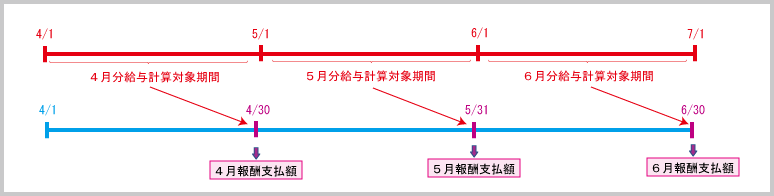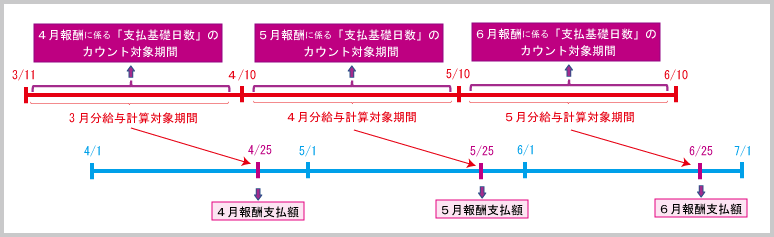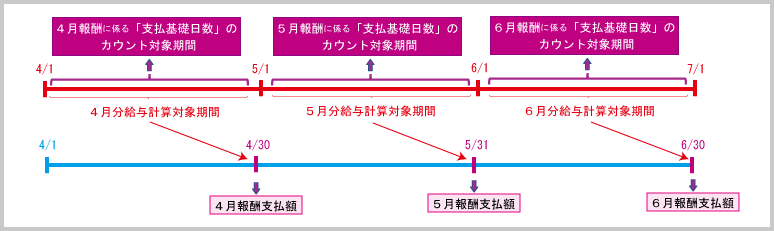ここでは、『「定時決定」における「報酬月額」の算定方法 』につきまして、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページの前提となる『「定時決定における標準報酬月額」の基礎的事項 』につきましては、
『 「標準報酬月額」の「定時決定」 』というページを御覧下さい。
Ⅰ:『 定時決定における「報酬月額」の算定 』のため必要となる事項
◆ 『「定時決定」における「報酬月額」』 ◆
『 定時決定時における「報酬月額」』とは、
|
|
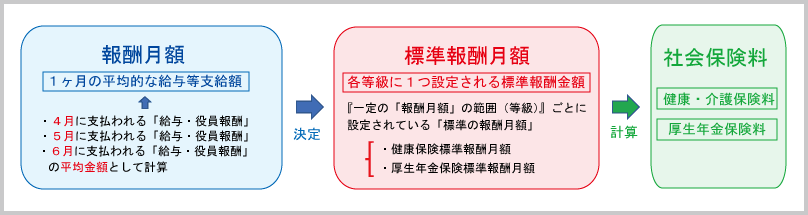
◆ 「報酬月額」を「3ヶ月平均金額」をもって算定する理由 ◆
◆ 「被保険者報酬月額算定基礎届」の届出 ◆
『 定時決定により決定される「標準報酬月額」』におきましては、最終的には社会保険の保険者が決定することとなりますが、
この保険者による「標準報酬月額」の決定がなされる前には、
|
「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載し、保険者に届出ることが必要となります。 |
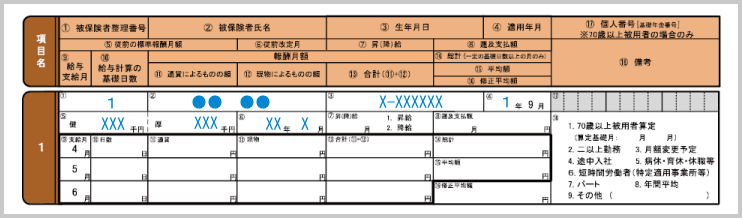
◆ 「被保険者報酬月額算定基礎届」の届出が必要となる理由 ◆
◆ 『 定時決定における「報酬月額」の算定 』のため必要となる事項 ◆
![]() 上記の「被保険者報酬月額算定基礎届」に「4月、5月、6月の給与・役員報酬の支払額」を適切に記載するためには、
上記の「被保険者報酬月額算定基礎届」に「4月、5月、6月の給与・役員報酬の支払額」を適切に記載するためには、
| 『「報酬月額」に含めなければならない「報酬(給与・役員報酬支給額)の範囲」』を適切に理解しておくことが必要となり、 |
![]() また、上記の「被保険者報酬月額算定基礎届」に
また、上記の「被保険者報酬月額算定基礎届」に
「4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた給与・役員報酬支給額の平均支払額(報酬月額)」を適切に記載するためには、
| 『「4月、5月、6月に支払われた給与・役員報酬支給額」を平均計算するための算定方法 』を適切に理解しておくことが必要となります。 |
![]() このため、当該ページにおきましては、
このため、当該ページにおきましては、
・ 下記Ⅱ にて、『 社会保険制度において「報酬となるもの」の範囲 』をご紹介させて頂くとともに、
・ 下記Ⅲ にて、『 定時決定における「報酬月額」の算定方法 』をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:「報酬月額」の算定対象となる『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』
1、社会保険において『「報酬となるもの」の範囲 』
![]() 「報酬月額」を算定する場合には、
「報酬月額」を算定する場合には、
| まず、『「報酬月額」の算定対象となる「報酬」の範囲 』を適切に把握しておくことが必要となりますが、 |
![]() この点、『「報酬月額」の算定対象となる「報酬(給与、役員報酬支給額)」』は、
この点、『「報酬月額」の算定対象となる「報酬(給与、役員報酬支給額)」』は、
|
「従業員・役員が労働・業務執行の対償として受ける全てのもの」が対象となり、
「通勤定期券の支給、食事の提供、社宅の貸与など現物で支給されるもの」も対象となります。 |
2、『「報酬月額」の算定対象となる「報酬」 』の具体的な項目
1)『「報酬月額」の算定対象となる「報酬」 』の具体的な項目
「日本年金機構」が公表する「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」では、
|
会社から従業員・役員に対して支給される「給与・役員報酬の内訳項目」を ・『 社会保険制度上「報酬月額」の算定対象に含めることが必要となるもの 』と 以下のように具体的に列挙しています。 |
| 「報酬月額」の算定対象となる支給額 | 「報酬月額」の算定対象とならない支給額 | |
| 金銭による支給 |
《 基本給 》
《 法定手当等 》
《 任意手当、その他 》 |
《 恩恵的支給 》
《 実費弁済的支給 》
《 臨時その他 》 |
| 現物による支給※1 | ・通勤定期券、回数券 ・食事、食券 ・社宅、寮 ・被服(勤務服でないもの) ・自社製品 |
・制服 ・作業着 ・見舞品 ・(会社負担が僅少な)食事など |
※ 「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」は、「日本年金機構のHP」からダウンロードできます。
◆ ※1:「現物給与」につきまして ◆
◆ ※2:「見舞金」につきまして ◆
◆ ※3:「賞与」につきまして ◆
◆ ※4:「出張旅費」につきまして ◆
◆ ※5:「交際費」につきまして ◆
2)『「報酬月額」の算定対象となる「報酬」 』についての留意点
◆ ①『「残業代」等の法定手当 』や「任意手当」についての留意点 ◆
『 定時決定における「報酬月額」』の算定におきましては、
|
・「基本給部分」だけではなく、 ・『「残業代」等の法定手当 』や「任意手当」が支給されている場合には、 |
◆ ②「現物給与」についての留意点 ◆
◆ 「現物給与」につきまして ◆
『 定時決定における「報酬月額」』の算定におきましては、
|
・『 金銭で支給される「給与」や「役員報酬」』だけではなく、 ・「食事等の提供・補助」「社宅等の貸与」などの「現物給与」が支給されている場合には、 |
◆ 「現物給与」の評価につきまして ◆
|
・「現物給与」につきましては、基本的には「現物支給されたものの時価」で評価しますが、 ・「食事等の提供・補助」「社宅等の貸与」につきましては、上記によらず、 |
◆ 「食事等の提供」と「社宅等の貸与」につきまして ◆
![]() 『「食事等の提供」に係る評価 』におきましては、
『「食事等の提供」に係る評価 』におきましては、
|
・ 当該「食事等」につき「従業員・役員がその費用の一部」を負担しており、 『 当該「食事等の提供」である「現物給与」』は「報酬月額」に含めなくてもよいという特別の規定が存在します。 |
![]() 他方、『「社宅等の貸与」に係る評価 』におきましては、
他方、『「社宅等の貸与」に係る評価 』におきましては、
|
・上記のような特別の規定は存在しないため、 ・『「社宅等の貸与」に係る評価額 の2/3以上 』を役員・従業員が負担している場合であっても、 |
◆ 「現物給与」の測定につきまして ◆
|
「現物給与」は、暦月単位で測定することになります。 例)「4月支払の報酬」には『「4月1日~4月30」に支給された「現物給与」』を「報酬月額」に含めることになります。 |
◆ ③「恩恵的な支給」「実費弁済的な支給」につきまして ◆
![]() 上記1)でご紹介させて頂きましたように、
上記1)でご紹介させて頂きましたように、
|
社会保険制度における『「報酬月額」の算定対象となる「報酬(給与、役員報酬支給額)」』は、 「従業員・役員が労働・業務執行の対償として受けるもの」が対象となるため、 |
『「給与」等に含めて支払われている支給額 』であっても、
| 『「労働・業務執行の対償」として支払われたものではない支給額 』は『「報酬月額」の算定対象 』とはなりません。 |
![]() このため、
このため、
|
・「大入袋」「見舞金」「慶弔費」などのように「恩恵的に支給されているもの」や 「労働・業務執行の対償」として支給されたものではないため『「報酬月額」の算定対象 』とはなりませんので、 「報酬月額」を算定する場合には、この点ご注意頂ますようお願いします。 |
◆ ④「税務上非課税となる給与・役員報酬」との違い (「通勤手当」「宿直・日直手当」) ◆
「通勤手当」「宿直・日直手当」につきましては、
|
一定の要件を満たせば、従業員・役員個人の課税所得金額から除外される「非課税支給額」となりますが、 |
|
・ 上記『 税務上のような「特別な措置」』はなく、 ・「非課税通勤手当」「非課税宿直・日直手当」であっても「報酬月額」に含めることが必要となりますので、 「報酬月額」を算定する場合には、この点混同なされないようご注意下さい。 |
Ⅲ:定時決定における『「報酬月額」の算定方法 』(全般的内容)
1、『 定時決定における「報酬月額」』の「原則的な算定方法」と「例外的な算定方法」
◆ 原則的な算定方法 ◆
![]() 『 定時決定における「報酬月額」』につきましては、
『 定時決定における「報酬月額」』につきましては、
| 原則的には『 4月、5月、6月に支払われた「給与・役員報酬支給額」』を平均することにより算定されます。 |
![]() このため、『 定時決定における「報酬月額」』を算定する場合には、
このため、『 定時決定における「報酬月額」』を算定する場合には、
|
原則、 ①『 4月に支払われた「給与・役員報酬支給額」』 『 5月に支払われた「給与・役員報酬支給額」』 『 6月に支払われた「給与・役員報酬支給額」』を合計し、
②『 上記3ヶ月間の給与・役員報酬支給額の合計額 』を「3ヶ月」で除すことにより「報酬月額」を算定します。 |
◆ 「4月、5月、6月に支払われた給与・役員報酬支給額」とは ◆
◆ 例外的な算定方法 ◆
![]() ただし、『 定時決定における「報酬月額」』は、
ただし、『 定時決定における「報酬月額」』は、
| 『 保険年度を通じて「1ヶ月の給与・役員報酬支給額を代表するような金額」』として計算することが望ましいため、 |
「4月~6月」の3ヶ月の内に「通常月に比べ給与・役員報酬支給額が低い月」が存在するような場合には、
| 「その月に支払われた給与・役員報酬支給額」を除いて「1ヶ月の平均報酬額(報酬月額)」を算定することが必要となります。 |
![]() このため、社会保険制度上におきましては、
このため、社会保険制度上におきましては、
|
「その月の給与・役員報酬支給額」は除いて「報酬月額」を算定することとしています。 |
2、『「支払基礎日数」の意義 』と『「支払基礎日数」のカウント方法」』
1)「支払基礎日数」の意義
![]() 「支払基礎日数」とは、
「支払基礎日数」とは、
| 「その月に支払われた給与・役員報酬支給額」の「計算・支給対象となった日数」のことをいいますが、 |
![]() 当該「支払基礎日数」は、
当該「支払基礎日数」は、
|
「その月に支払われた給与等の支給額」が、 『「他の月に支払われた給与等の支給額」に比べて低い金額となっていないか? 』を判定するために利用されるものであり、 |
『 その月の「支払基礎日数」』が「他の月の「支払基礎日数」に比べて少なくなっているような場合には、
|
「その月に支払われた給与等の支給金額」は、 『「他の月に支払われた給与等の支給金額」に比べて低い金額になっている 』と推定判定されることになります。 |
2)「支払基礎日数」のカウント方法
◆ ①「支払基礎日数」の「カウント対象となる期間」 ◆
|
上記1)の脚注でご紹介させて頂きましたように、 ・「4月の報酬」は「4月に支払われた給与・役員報酬支給額」をいい、 |
|
『「4月に支払われた給与・役員報酬支給額」の計算対象期間」を対象としてカウントすることになり、
『「5月に支払われた給与・役員報酬支給額」の計算対象期間」を対象としてカウントすることになり、
『「6月に支払われた給与・役員報酬支給額」の計算対象期間」を対象としてカウントすることになります。 |
◆ 『「支払基礎日数」のカウント期間 』の例示 ◆
◆ ②「支払基礎日数」のカウント方法 ◆
![]() 『「支払基礎日数」のカウント方法 』につきましては、
『「支払基礎日数」のカウント方法 』につきましては、
日本年金機構が公表している「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」に、
|
|
というように『「支払基礎日数」のカウント方法 』が記載されているため、
![]() 『「支払基礎日数」のカウント方法 』は、
『「支払基礎日数」のカウント方法 』は、
|
「暦日数」によりカウントすることが必要となり、
『「所定労働日数」から「欠勤日数」を「控除した日数」』でカウントすることが必要となり、
「実際の出勤日数」によりカウントすることが必要となります。 |
▶ なお、『「支払基礎日数」のカウント方法 』は「下記 Ⅳ ~ Ⅶ 」で個別に詳しくご紹介させて頂いております。
3、『「報酬月額」の算定 』における『「支払基礎日数」の(最低日数)要件 』
![]() 上記1でご紹介させて頂きましたように
上記1でご紹介させて頂きましたように
|
「報酬月額」を『「原則的な方法」で算定するのか 』又は『「例外的な方法」で算定するのか 』につきましては、 『「支払基礎日数」に「最低日数要件」』を設けて判定することとしていますが、 |
![]() そもそも「1ヶ月の間に出勤・労働することが予定されている日数」につきましては、
そもそも「1ヶ月の間に出勤・労働することが予定されている日数」につきましては、
|
・その従業員等が『 フルタイムで出勤・労働することが予定されている「正社員」』であるのか? ・その従業員等が『 フルタイムで出勤・労働することが予定されていない「パート社員など」』であるのか? により違いがあることから、 |
制度上におきましては、
|
この「支払基礎日数の(最低日数)要件」を「17日以上」と規定し、
この「支払基礎日数の(最低日数)要件」を「17日以上」又は「15日以上」と規定し、
この「支払基礎日数の(最低日数)要件」を「11日以上」と規定し、
『「報酬月額の平均計算に含めるべき月」の「支払基礎日数要件」』を従業員等の雇用形態ごと別々に規定しています。 |
▶ なお、『「支払基礎日数」の要件 』は「下記 Ⅳ ~ Ⅶ 」で個別に詳しくご紹介させて頂いております。
4、「報酬月額」の算定手順と算定方法
上記1から3でご紹介させて頂きました事項をまとめると、「報酬月額」につきましては以下の手順で算定することになります。
Step1:「従業員等」の「雇用形態」の区分把握
まず最初に、「定時決定の対象となる被保険者」が
|
・「役員」であるのか? ・「正社員(フルタイム労働者)」であるのか? ・「パート社員等の短時間就労者」であるのか? ・「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」であるのか? を区分把握します。 |
Step2:『「給与支給形態」の区分把握 』及び『「支払基礎日数」のカウント 』
![]() 次に、「役員」である「被保険者」につきましては、
次に、「役員」である「被保険者」につきましては、
| 「4月、5月、6月の暦日数」を「支払基礎日数」としてカウントし、 |
![]() 「正社員」「短時間就労者」「短時間労働者」である「(従業員)被保険者」につきましては、
「正社員」「短時間就労者」「短時間労働者」である「(従業員)被保険者」につきましては、
|
・「給与」が「完全月給制」や「完全週給制」により支給されているのか? ・「給与」が「月給日給制」や「週給日給制」により支給されているのか? ・「給与」が「日給制」や「時給制」により支給されているのか? を把握し、 |
| それぞれの『「給与等の支給形態」に応じたカウント方法 』により『 4月~6月の「支払基礎日数」』をカウントします。 |
Step3:『「支払基礎日数要件」の判定 』及び『「報酬月額」の算定 』
![]() 最後に、「役員」である「被保険者」につきましては、
最後に、「役員」である「被保険者」につきましては、
| 「原則的な算定方法」により「報酬月額」を算定し、 |
![]() 「正社員」「短時間就労者」「短時間労働者」である「(従業員)被保険者」につきましては、
「正社員」「短時間就労者」「短時間労働者」である「(従業員)被保険者」につきましては、
|
「原則的な算定方法」により「報酬月額」を算定し、
「例外的な算定方法」により「報酬月額」を算定します。 |
5、以下「 ⅣからⅦ でご紹介させて頂く内容」につきまして
当該箇所では、『 定時決定における「報酬月額」の算定方法 』についての「全般的な内容」をご紹介させて頂きましたが、
以下におきましては、
・ 下記Ⅳ で「役員」における『「報酬月額」の算定方法 』を
・ 下記Ⅴ で「正社員」における『「報酬月額」の算定方法 』を
・ 下記Ⅵ で「パート従業員等(短時間就労者)」における『「報酬月額」の算定方法 』を
・ 下記Ⅶ で「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」における『「報酬月額」の算定方法 』を
それぞれ個別にご紹介させて頂きます。
Ⅳ:「役員」における『「報酬月額」の算定方法 』
1、「役員」とは
「役員」とは、
|
「取締役」「監査役」などの 会社との「経営委任契約」に基づき、会社経営業務・経営監督業務等を行っている者をいいます。 |
2、「役員」における『「支払基礎日数」のカウント方法 』
◆ 「役員」における『「支払基礎日数」のカウント方法 』 ◆
『「役員」における「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月の各月の暦日数」でカウントすることになり、 |
|
・「4月の役員報酬に係る支払基礎日数」は30日となり、 ・「5月の役員報酬に係る支払基礎日数」は31日となり、 ・「6月の役員報酬に係る支払基礎日数」は30日となります。 |
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
3、「役員」における『「報酬月額」の算定方法 』
![]() 『「役員」に支給される「役員報酬」』につきましては、
『「役員」に支給される「役員報酬」』につきましては、
|
・(上記2でご紹介させて頂きましたように、)「各月の暦日数」を「支払基礎日数」としてカウントするため、 ・「4月~6月」の3ヶ月の内に「通常月に比べ役員報酬支給額が低い月」は存在しないことになります。 |
![]() このため、「役員」における『「報酬月額」の算定 』では、
このため、「役員」における『「報酬月額」の算定 』では、
|
|
|
①『 4月に支払われた「役員報酬支給額」』 『 5月に支払われた「役員報酬支給額」』 『 6月に支払われた「役員報酬支給額」』を合計し、
②『 上記3ヶ月間の役員報酬支給額の合計額 』を「3ヶ月」で除すことにより「報酬月額」を計算することになります。 |
Ⅴ:「正社員」における『「報酬月額」の算定方法 』
![]() 「正社員」とは、
「正社員」とは、
| その会社で「フルタイム」の基幹的な働き方をしている労働者をいいますが、 |
![]() この「正社員」につきましては、
この「正社員」につきましては、
| 「給与の支給」につき「完全月給制が採用されている場合」と「月給日給制が採用されている場合」とがあり、 |
「完全月給制が採用されている正社員」と「月給日給制が採用されている正社員」とでは、
| 『「支払基礎日数」のカウント方法 』や『「報酬月額」の算定方法 』に違いがあることから、 |
![]() 以下におきましては、
以下におきましては、
| 「完全月給制の正社員」と「月給日給制の正社員」とに分けてご紹介させて頂きます。 |
※ なお、「正社員」につき「週給制、日給制、時給制などの給与支給形態」が採用されていることも理論上は想定されますが、
実務上「正社員」に「週給制、日給制、時給制」が採用されることは殆どないためここでの紹介は省略させて頂きます。
1、「完全月額制の正社員」における『「報酬月額」の算定方法 』
1)「完全月給制の正社員」とは
「完全月給制の正社員」とは、
|
|
2)「完全月額制の正社員」における『「支払基礎日数」のカウント方法 』
『「完全月給制の正社員」における「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月に支払われた給与の計算対象期間」における「暦日数」でカウントすることになり、 |
|
・「4月の支払基礎日数」は「4月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となり、 ・「5月の支払基礎日数」は「5月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となり、 ・「6月の支払基礎日数」は「6月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となります。 |
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
3)「完全月給制の正社員」における『「報酬月額」の算定方法 』
![]() 『「完全月給制の正社員」に支給される「給与」』につきましては、
『「完全月給制の正社員」に支給される「給与」』につきましては、
|
・上記2)でご紹介させて頂きましたように、 ・「4月~6月」の3ヶ月の内に「通常月に比べ給与支給額が低い月」は存在しないことになります。 |
![]() このため、「完全月給制の正社員」における『「報酬月額」の算定 』では、
このため、「完全月給制の正社員」における『「報酬月額」の算定 』では、
|
|
|
①『 4月に支払われた「給与支給額」』 『 5月に支払われた「給与支給額」』 『 6月に支払われた「給与支給額」』を合計し、
②『 上記3ヶ月間の給与支給額の合計額 』を「3ヶ月」で除すことにより「報酬月額」を計算することになります。 |
2、「月給日給制の正社員」における『「報酬月額」の算定方法 』
1)「月給日給制の正社員」とは
「月給日給制の正社員」とは、
|
|
2)「月額日給制の正社員」における『「支払基礎日数」のカウント方法 』
『「月給日給制の正社員」における「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月に支払われた給与の計算対象期間」における 『「所定労働日数」から「欠勤日数」を「控除した日数」』でカウントすることになり、 |
|
・「4月の支払基礎日数」は、 ・「5月の支払基礎日数」は、 ・「6月の支払基礎日数」は、 |
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
3)「報酬月額」の算定対象となるための『「支払基礎日数」の要件 』
![]() 「月給日給制の正社員」につきましては、
「月給日給制の正社員」につきましては、
| その会社において「フルタイム」で働いていることが想定されることから、 |
制度上、『「通常月に比べ給与支給額が低い月」であるか否か 』の判定につきましては、
| 『 その月の「支払基礎日数」』が「17日以上あるかないか」によって判定することとされます。 |
![]() このため、「月給日給制の正社員」につきましては、
このため、「月給日給制の正社員」につきましては、
|
「その月に支給された給与」は「報酬月額」の平均計算に含められますが、
「その月に支給された給与」は |
4)「月給日給制の正社員」における『「報酬月額」の算定方法 』
「月給日給制の正社員」につきましては、
|
『 上記3)でご紹介させて頂きました「支払基礎日数の要件」』を考慮して、以下のように算定することが必要となります。 |
◆ 原則的な算定方法 ◆
『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がいずれも「17日以上」ある場合には、
|
( 4月に支払われた給与支給額 + 5月に支払われた給与支給額 + 6月に支払われた給与支給額 ) ÷ 3ヶ月 という計算式で「報酬月額」を算定します。 |
◆ 例外的な算定方法 ◆
![]() 『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか2ヶ月の「支払基礎日数」』が「17日以上」ある場合には、
『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか2ヶ月の「支払基礎日数」』が「17日以上」ある場合には、
|
『「支払基礎日数が17日以上ある2ヶ月の給与支給額」の合計金額 』 ÷ 2ヶ月 という計算式で「報酬月額」を算定します。 |
![]() 『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか1ヶ月の「支払基礎日数」』が「17日以上」ある場合には、
『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか1ヶ月の「支払基礎日数」』が「17日以上」ある場合には、
|
「支払基礎日数が17日以上ある月の給与支給額」 が「報酬月額」となります。 |
◆ 保険者が決定する場合 ◆
なお『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がすべて「17日未満」である場合には、
|
|
Ⅵ:「パート社員等の短時間就労者」における『「報酬月額」の算定方法 』
1、「パート社員等の短時間就労者」とは
「短時間就労者」とは、
|
|
2、「パート社員等の短時間就労者」における『「支払基礎日数」のカウント方法 』
『「パート社員等の短時間就労者」に支給される「給与」』につきましては、
|
①「完全月給制」「完全週給制」 ②「月給日給制」「週給日給制」 ③「日給制」「時給制」など 様々な形態で給与が支給されていることが考えられますが、 |
「パート社員等の短時間就労者」につきましては、
| 「上記①から③の給与支給形態ごと」に「異なる方法」により「支払基礎日数」をカウントすることが必要となります。 |
◆ ①「完全月給制」や「完全週給制」が採用されている場合 ◆
『「完全月給制」や「完全週給制」が採用されている場合の「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月に支払われた給与の計算対象期間」における「暦日数」でカウントすることになり、 |
|
・「4月の支払基礎日数」は「4月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となり、 ・「5月の支払基礎日数」は「5月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となり、 ・「6月の支払基礎日数」は「6月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となります。 |
◆ 「完全月給制」「完全週給制」とは ◆
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
◆ ②「月給日給制」や「週給日給制」が採用されている場合 ◆
『「月給日給制」や「週給日給制」が採用されている場合の「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月に支払われた給与の計算対象期間」における 『「所定労働日数」から「欠勤日数」を「控除した日数」』でカウントすることになり、 |
| ・「4月の支払基礎日数」は、 「4月に支払われた給与の計算対象期間」における『「所定労働日数」から「欠勤日数」を「控除した日数」』となり、 ・「5月の支払基礎日数」は、 ・「6月の支払基礎日数」は、 |
◆ 「月給日給制」「週給日給制」とは ◆
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
◆ ③「日給制」や「時給制」が採用されている場合 ◆
『「日給制」や「時給制」が採用されている場合の「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月に支払われた給与の計算対象期間」における 「実際の出勤日数(有給休暇も含みます。)」でカウントすることになり、 |
| ・「4月の支払基礎日数」は「4月に支払われた給与の計算対象期間における出勤日数」となり、
・「5月の支払基礎日数」は「5月に支払われた給与の計算対象期間における出勤日数」となり、 ・「6月の支払基礎日数」は「6月に支払われた給与の計算対象期間における出勤日数」となります。 |
◆ 「日給制」「時給制」とは ◆
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
3、「報酬月額」の算定対象となるための『「支払基礎日数」の要件 』
「パート社員等の短時間就労者」に対しては、
| 以下のように2段階で『「報酬月額」の算定対象となるための「支払基礎日数の要件」 』が規定されています。 |
◆ 第1段階の判定( 「支払基礎日数」が「17日以上の月」が1ヶ月でもある場合 ) ◆
第1段階の判定としては、
|
『「4月、5月、6月における「支払基礎日数」』が「17日以上ある月」が1ヶ月でもある場合には、 (正社員の場合と同様に)「支払基礎日数が17日以上ある月」を対象として「報酬月額」を算定します。 |
すなわち、
・『「4月、5月、6月における「支払基礎日数」』が「17日以上ある月」が1ヶ月でもある場合には、
|
|
◆ 第2段階の判定( 「すべての月の支払基礎日数」が17日未満の場合 ) ◆
第2段階の判定としては、
|
・『「4月、5月、6月における「すべての支払基礎日数」』が「17日未満」となる場合であっても、 ・『「4月、5月、6月における「支払基礎日数」』が「15日以上ある月」が1ヶ月でもある場合には、 「支払基礎日数が15日以上ある月」を対象として「報酬月額」を算定します。 |
すなわち、
・『「4月、5月、6月における「すべての支払基礎日数」』が「17日未満」となる場合であっても、
・『「4月、5月、6月における「支払基礎日数」』が「15日以上ある月」が1ヶ月でもある場合には、
|
|
◆ 上記規定の理由 ◆
4、「パート等の短時間就労者」における『「報酬月額」の算定方法 』
「パート社員等の短時間就労者」につきましては、
|
上記2でご紹介させて頂きましたように、 『「支払基礎日数」のカウント方法 』が、 ・「完全月給制・完全週給制」を採用している場合のように「固定的な暦日数」でにカウントされるものと、 ・「月給日給制・週給日給制」や「日給制・時給制」を採用している場合のように「可変的な日数」でカウントされるものとに分かれるため、 |
以下『「報酬月額」の算定方法 』につきましては、
|
・「完全月給制・完全週給制」を採用している場合における『「報酬月額」の算定方法 』と ・「月給日給制・週給日給制」「日給制・時給制」を採用している場合における『「報酬月額」の算定方法 』に分けてご紹介させて頂きます。 |
1) 「完全月給制・完全週給制」を採用している場合
![]() ( 実務上では「レアなケース」になるとは思いますが、)
( 実務上では「レアなケース」になるとは思いますが、)
「パート社員等の短時間就労者の給与」につき「完全月給制・完全週給制」を採用している場合には、
|
・上記2①でご紹介させて頂きましたように、 ・「4月~6月」の3ヶ月の内に「通常月に比べ給与支給額が低い月」は存在しないことになります。 |
![]() このため、「完全月給制・完全週給制」を採用している場合における『「報酬月額」の算定 』では、
このため、「完全月給制・完全週給制」を採用している場合における『「報酬月額」の算定 』では、
|
|
|
①『 4月に支払われた「給与支給額」』 『 5月に支払われた「給与支給額」』 『 6月に支払われた「給与支給額」』を合計し、
②『 上記3ヶ月間の給与支給額の合計額 』を「3ヶ月」で除すことにより「報酬月額」を計算することになります。 |
2) 「月給日給制・週給日給制」「日給制・時給制」を採用している場合
![]() ( 実務上では「こちらがメイン」になると思いますが、)
( 実務上では「こちらがメイン」になると思いますが、)
「パート社員等の短時間就労者の給与」につき「月給日給制・週給日給制」や「日給制・時給制」を採用している場合には、
|
『 上記3でご紹介させて頂きました「支払基礎日数の要件」』を考慮して、以下のように『 段階的に「報酬月額」を算定する 』ことが必要となります。 |
◆ 第1段階の判定 ◆
原則的な算定方法
『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がいずれも「17日以上」ある場合には、
|
( 4月に支払われた給与支給額 + 5月に支払われた給与支給額 + 6月に支払われた給与支給額 ) ÷ 3ヶ月 という計算式で「報酬月額」を算定します。 |
例外的な算定方法
![]() 『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか2ヶ月の「支払基礎日数」』が「17日以上」ある場合には、
『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか2ヶ月の「支払基礎日数」』が「17日以上」ある場合には、
|
『「支払基礎日数が17日以上ある2ヶ月の給与支給額」の合計金額 』 ÷ 2ヶ月 という計算式で「報酬月額」を算定します。 |
![]() 『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか1ヶ月の「支払基礎日数」』が「17日以上」ある場合には、
『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか1ヶ月の「支払基礎日数」』が「17日以上」ある場合には、
|
「支払基礎日数が17日以上ある月の給与支給額」 が「報酬月額」となります。 |
◆ 第2段階の判定 ◆
原則的な算定方法
・『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がいずれも「17日未満」であるが、
・『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がいずれも「15日以上」ある場合には、
|
( 4月に支払われた給与支給額 + 5月に支払われた給与支給額 + 6月に支払われた給与支給額 ) ÷ 3ヶ月 という計算式で「報酬月額」を算定します。 |
例外的な算定方法
![]() 「支払基礎日数が15日以上ある月」が2ヶ月ある場合
「支払基礎日数が15日以上ある月」が2ヶ月ある場合
・『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がいずれも「17日未満」であるが、
・『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか2ヶ月の「支払基礎日数」』が「15日以上」ある場合には、
|
『「支払基礎日数が15日以上ある2ヶ月の給与支給額」の合計金額 』 ÷ 2ヶ月 という計算式で「報酬月額」を算定します。 |
![]() 「支払基礎日数が15日以上ある月」が1ヶ月のみの場合
「支払基礎日数が15日以上ある月」が1ヶ月のみの場合
・『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がいずれも「17日未満」であるが、
・『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか1ヶ月の「支払基礎日数」』が「15日以上」ある場合には、
|
「支払基礎日数が15日以上ある月の給与支給額」 が「報酬月額」となります。 |
◆ 保険者が決定する場合 ◆
なお『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がすべて「15日未満」である場合には、
|
|
Ⅶ:「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」における『「報酬月額」の算定方法 』
1、「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」とは
「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」とは、
|
|
◆ 「特定適用事業所」とは ◆
◆ 「短時間労働者」の要件 ◆
2、「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」における『「支払基礎日数」のカウント方法 』
『「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」に支給される「給与」』につきましては、
|
①「完全月給制」「完全週給制」 ②「月給日給制」「週給日給制」 ③「日給制」「時給制」など 様々な形態で給与が支給されていることが考えられますが、 |
「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」につきましては、
| 「上記①から③の給与支給形態ごと」に「異なる方法」により「支払基礎日数」をカウントすることが必要となります。 |
◆ ①「完全月給制」や「完全週給制」が採用されている場合 ◆
『「完全月給制」や「完全週給制」が採用されている場合の「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月に支払われた給与の計算対象期間」における「暦日数」でカウントすることになり、 |
|
・「4月の支払基礎日数」は「4月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となり、 ・「5月の支払基礎日数」は「5月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となり、 ・「6月の支払基礎日数」は「6月に支払われた給与の計算対象期間における暦日数」となります。 |
◆ 「完全月給制」「完全週給制」とは ◆
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
◆ ②「月給日給制」や「週給日給制」が採用されている場合 ◆
『「月給日給制」や「週給日給制」が採用されている場合の「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月に支払われた給与の計算対象期間」における 『「所定労働日数」から「欠勤日数」を「控除した日数」』でカウントすることになり、 |
| ・「4月の支払基礎日数」は、 「4月に支払われた給与の計算対象期間」における『「所定労働日数」から「欠勤日数」を「控除した日数」』となり、 ・「5月の支払基礎日数」は、 ・「6月の支払基礎日数」は、 |
◆ 「月給日給制」「週給日給制」とは ◆
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
◆ ③「日給制」や「時給制」が採用されている場合 ◆
『「日給制」や「時給制」が採用されている場合の「支払基礎日数」』は、
| 「4月、5月、6月に支払われた給与の計算対象期間」における 「実際の出勤日数(有給休暇も含みます。)」でカウントすることになり、 |
| ・「4月の支払基礎日数」は「4月に支払われた給与の計算対象期間における出勤日数」となり、
・「5月の支払基礎日数」は「5月に支払われた給与の計算対象期間における出勤日数」となり、 ・「6月の支払基礎日数」は「6月に支払われた給与の計算対象期間における出勤日数」となります。 |
◆ 「日給制」「時給制」とは ◆
◆ 上記のようにカウントする理由 ◆
3、「報酬月額」の算定対象となるための『「支払基礎日数」の要件 』
「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」につきましては、
|
「1週間の所定労働時間」又は「1か月の所定労働日数」が、 「同じ事業所で同様の業務に従事している正社員」の「4分の3未満」であるような労働者であることから、 |
制度上、『「通常月に比べ給与支給額が低い月」であるか否か 』の判定につきましては、
| 『「正社員」や「短時間就労者」に対して設定されている判定基準 』よりも低い水準で判定することが必要となり、 |
『「通常月に比べ給与支給額が低い月」であるか否か 』は、
| 『 その月の「支払基礎日数」』が「11日以上あるかないか」によって判定することとされます。 |
![]() このため、「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」につきましては、
このため、「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」につきましては、
|
「その月に支給された給与」は「報酬月額」の平均計算に含められますが、
「その月に支給された給与」は |
4、「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」における『「報酬月額」の算定方法 』
「(特定適用事業所に勤務する)短時間労働者」につきましては、
|
上記2でご紹介させて頂きましたように、 『「支払基礎日数」のカウント方法 』が、 ・「完全月給制・完全週給制」を採用している場合のように「固定的な暦日数」でにカウントされるものと、 ・「月給日給制・週給日給制」や「日給制・時給制」を採用している場合のように「可変的な日数」でカウントされるものとに分かれるため、 |
以下『「報酬月額」の算定方法 』につきましては、
|
・「完全月給制・完全週給制」を採用している場合における『「報酬月額」の算定方法 』と ・「月給日給制・週給日給制」「日給制・時給制」を採用している場合における『「報酬月額」の算定方法 』に分けてご紹介させて頂きます。 |
1)「完全月給制・完全週給制」を採用している場合
![]() ( 実務上では「レアなケース」になるとは思いますが、)
( 実務上では「レアなケース」になるとは思いますが、)
「短時間労働者の給与」につき「完全月給制・完全週給制」を採用している場合には、
|
・上記2①でご紹介させて頂きましたように、 ・「4月~6月」の3ヶ月の内に「通常月に比べ給与支給額が低い月」は存在しないことになります。 |
![]() このため、「完全月給制・完全週給制」を採用している場合における『「報酬月額」の算定 』では、
このため、「完全月給制・完全週給制」を採用している場合における『「報酬月額」の算定 』では、
|
|
|
①『 4月に支払われた「給与支給額」』 『 5月に支払われた「給与支給額」』 『 6月に支払われた「給与支給額」』を合計し、
②『 上記3ヶ月間の給与支給額の合計額 』を「3ヶ月」で除すことにより「報酬月額」を計算することになります。 |
2) 「月給日給制・週給日給制」「日給制・時給制」を採用している場合
![]() ( 実務上では「こちらがメイン」になると思いますが、)
( 実務上では「こちらがメイン」になると思いますが、)
「短時間労働者の給与」につき「月給日給制・週給日給制」や「日給制・時給制」を採用している場合には、
|
『 上記3でご紹介させて頂きました「支払基礎日数の要件」』を考慮して、以下のように算定することが必要となります。 |
◆ 原則的な算定方法 ◆
『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がいずれも「11日以上」ある場合には、
|
( 4月に支払われた給与支給額 + 5月に支払われた給与支給額 + 6月に支払われた給与支給額 ) ÷ 3ヶ月 という計算式で「報酬月額」を算定します。 |
◆ 例外的な算定方法 ◆
![]() 『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか2ヶ月の「支払基礎日数」』が「11日以上」ある場合には、
『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか2ヶ月の「支払基礎日数」』が「11日以上」ある場合には、
|
『「支払基礎日数が11日以上ある2ヶ月の給与支給額」の合計金額 』 ÷ 2ヶ月 という計算式で「報酬月額」を算定します。 |
![]() 『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか1ヶ月の「支払基礎日数」』が「11日以上」ある場合には、
『「4月~6月に支払われた給与支給額」のいずれか1ヶ月の「支払基礎日数」』が「11日以上」ある場合には、
|
「支払基礎日数が11日以上ある月の給与支給額」 が「報酬月額」となります。 |
◆ 保険者が決定する場合 ◆
なお『「4月~6月に支払われた給与支給額」に対する「支払基礎日数」』がすべて「11日未満」である場合には、
|
|
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「定時決定」における「報酬月額」の算定方法 』をご紹介させて頂いております。
「報酬」に含めることが必要な「給与・役員報酬支給額の範囲」の確認
「報酬月額」を算定するためには、まず「4月、5月、6月に支払われた報酬」を集計・把握することが必要となりますが、
この点につきましては、上記Ⅱでご紹介させて頂きました内容をご確認頂き、
『「報酬」に含めなければならない給与・役員報酬支給額 』を適切に集計・把握して頂きますようお願い致します。
『「支払基礎日数」のカウント方法 』につきまして
「支払基礎日数」は、『「報酬月額」の算定対象に含めるか否かの「判定基準」』となる重要なものとなります。
このため、
・「上記Ⅲ-2でご紹介させて頂きました内容」や
・『 Ⅳ~Ⅶでご紹介させて頂きました「各雇用形態ごとの支払基礎日数のカウント方法」』をご確認頂き、
適切に「支払基礎日数」のカウントを行って頂ますようお願い致します。
なお、『「支払基礎日数」のカウント方法 』につきましては『「給与の支給形態ごと」に「異なる方法」でカウントする 』ことが必要となりますので、この点につきましては十分ご留意頂ますようお願い致します。
『「報酬月額」の算定方法 』につきまして
『「報酬月額」の算定方法 』につきましては、
・上記Ⅲ-1でご紹介させて頂きましたように「原則的な算定方法」と「例外的な算定方法」がありますので、
「報酬月額」を算定する場合には、まずこの点をご確認頂ますようお願い致します。
・また、『「原則的な方法」で「報酬月額」を算定するのか?』『「例外的な方法」で「報酬月額」を算定するのか?』は、
上記Ⅲ-3でご紹介させて頂きましたように『「従業員の雇用形態(被保険者の身分)ごと」に「異なる支払基礎日数要件」』が設けられておりますので、この点ご確認頂ますようお願い致します。
( 特に、『「パート社員などの短時間就労者」の「支払基礎日数要件」』につきましては「2段階の判定」が設けられておりますので、この点につきましては十分ご留意頂ますようお願い致します。)
・そして最後に、「上記の点」や『 Ⅳ~Ⅶでご紹介させて頂きました「従業員の雇用形態ごとの報酬月額の算定方法」』をご確認頂き、適切に「報酬月額」を算定して頂ますようお願い致します。